※本ページはプロモーションが含まれています。
遺言書は「書いて終わり」ではない
「遺言書を書こう」と思い立ったとき、多くの方は「どんな文面にしようか」と真っ先に考えます。
しかし、行政書士としての経験から申し上げれば、文面を作成することは、遺言という長いプロセスのほんの一部に過ぎません。
遺言書は、あなたが亡くなった後に、その意志が正確に、そしてスムーズに実行されて初めて価値を持ちます。
そのためには、作成前の徹底的な調査、法的な形式の遵守、そして執行(手続きの実行)を見据えた準備という、「点」ではなく「線」の設計が必要不可欠です。
2024年4月に施行された相続登記の義務化や、2025年現在、社会問題化しているデジタル資産の放置など、現代の相続環境はかつてないほど複雑化しています。
不備のある遺言書は、残された家族に「罰則」や「紛争」という負の遺産を押し付けることになりかねません。
今回は、専門家がどのように遺言書を創り上げ、どのようにそれを現実の形にするのか。
その全行程を徹底的に解剖します。
意志を「法的根拠」に変える!
事前調査(準備編)
遺言書作成の第一歩は、ペンを執ることではなく、事実を確認することから始まります。
財産の「棚卸し」とデジタル資産の捕捉
まずは、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべて洗い出します。
特に2025年現在の重要課題は、デジタル遺産です。
- ネット銀行、ネット証券の口座
- 暗号資産(仮想通貨)
- 有料サブスクリプションの契約状況

不動産の「精査」と地番の確認
日常使っている「住所」では、法務局での登記手続きはできません。
登記事項証明書(登記簿)を取得し、地番・家屋番号を確認します。
特に私道や未登記の建物、古い抵当権が残っていないかを精査することは、2024年からの相続登記義務化に対応するために必須の作業です。

推定相続人の「確定」
「自分の子供は3人だけだ」と思っていても、戸籍を遡ると予期せぬ事実(前妻との子供や認知した子供など)が判明することが稀にあります。
行政書士は、職権で出生から現在までの連続した戸籍を取得し、相続関係図を作成して、法的に誰が相続人になるのかを100%確定させます。
紛争を防ぎ、意志を通す!
文案作成(設計編)
事実関係が整理できたら、次は「誰に何を、なぜ渡すのか」という設計図を描きます。
遺留分(いりゅうぶん)への配慮と対策
特定の相続人に多くの財産を継がせたい場合、他の相続人が持つ「最低限の取り分(遺留分)」を侵害する可能性があります。
これを無視すると、死後に遺留分侵害額請求という裁判沙汰に発展しかねません。
行政書士は、遺留分を考慮した配分にするか、あるいは遺留分を侵害してでも渡したい場合には、その代償金の準備方法(生命保険の活用など)をアドバイスします。

「付言事項(ふげんじこう)」で想いを伝える
遺言書には、財産分与だけでなく、自分の想いを綴るメッセージ欄を設けることができます。
「なぜ、このような配分にしたのか」「家族にどのような未来を歩んでほしいのか」 法的な拘束力はありませんが、この一言が相続人の心を動かし、紛争を未然に防ぐ強力な心理的効果を発揮します。
予備的遺言(よびてきゆいごん)の活用
「財産を継がせる予定だった人が、自分より先に亡くなってしまったら?」
このような事態を想定し、「〇〇が先に亡くなった場合は、△△に相続させる」という予備的な条項を入れておくことで、遺言書が完全に無効化されるリスクを防ぎます。

「公正証書遺言」を完成させる!
当日の流れ(作成編)
以前にも解説した通り、最も確実なのは公証役場で作成する公正証書遺言です。
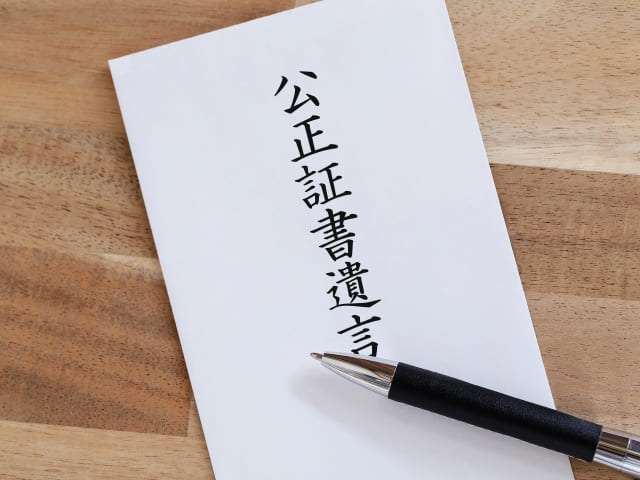
公証役場との事前調整
行政書士が文案を作成し、事前に公証人と打ち合わせを行います。
当日に内容で揉めることがないよう、法律的な解釈や用語の使い分けをプロ同士ですり合わせておきます。
証人(しょうにん)の確保
公正証書遺言の作成には、2人の証人の立ち会いが必要です。
親族は証人になれないため、当事務所では、守秘義務を持つプロのスタッフが証人を務めます。
これにより、プライバシーを守りつつ、手続きを円滑に進めることができます。
作成当日の手続き
公証人が遺言者に内容を読み上げ、本人に間違いがないかを確認します。
署名・捺印を行い、手数料を支払えば、その場で「正本」と「謄本」が手渡されます。
原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失の心配はありません。
作成後のメンテナンス!
法改正への対応(管理編)
遺言書は一度作れば一生安心、というわけではありません。
状況の変化に合わせた書き直し
- 財産の内容が大きく変わった(家を売った、大金を手にしたなど)
- 受取人の状況が変わった(離婚、再婚、先逝など)
- 自分の気持ちが変わった
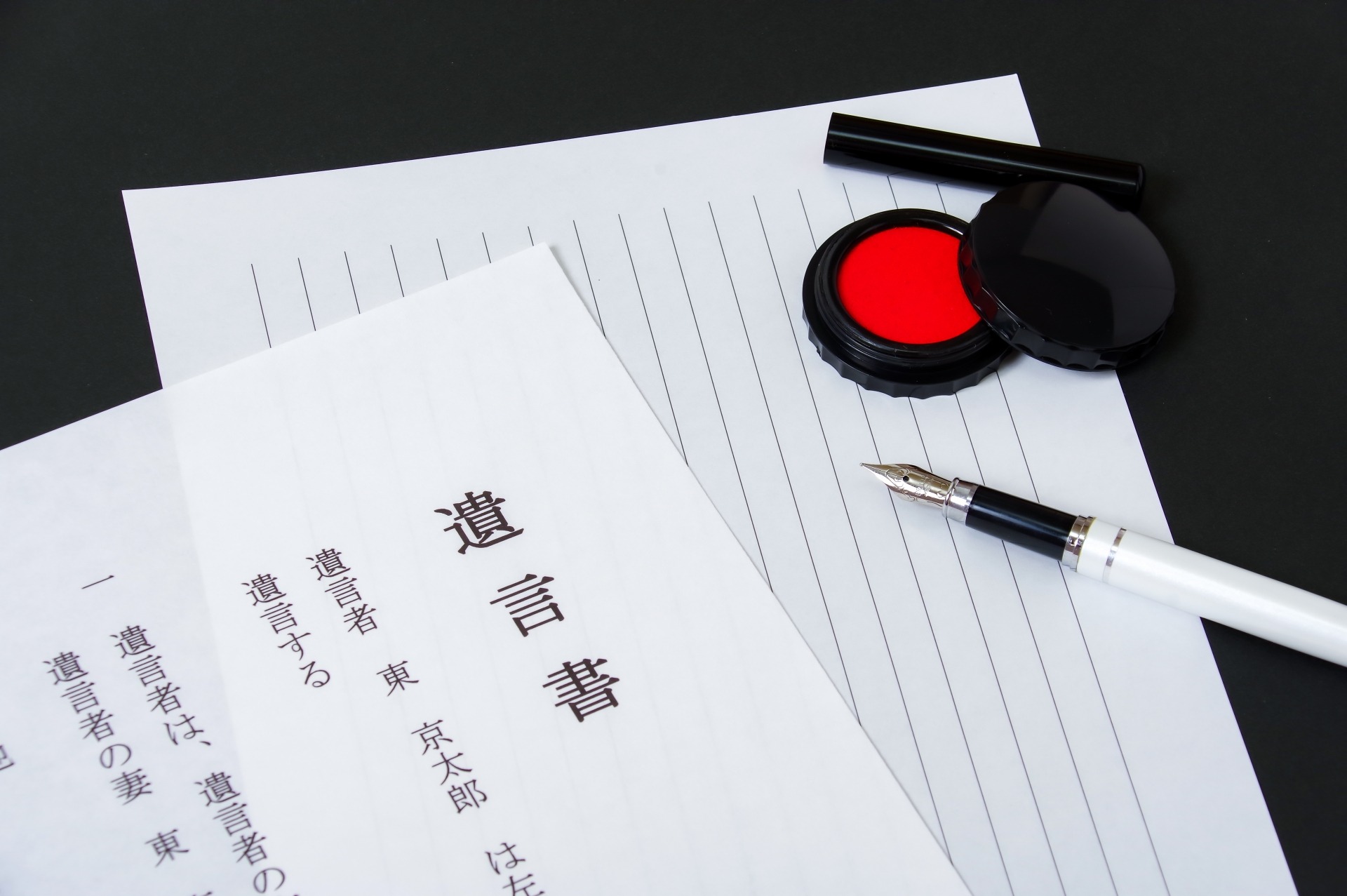
2024年相続登記義務化への再確認
古い遺言書をお持ちの方で、不動産の特定が曖昧(住居表示のみの記載など)な場合、現在の法務局の基準では登記が通らない可能性があります。
義務化による過料(罰則)を避けるためにも、最新の基準で文面をチェックすることが推奨されます。

ついに訪れる「その時」
遺言が現実になる瞬間(執行編)
遺言書が真価を発揮するのは、相続が発生した瞬間です。
ここでは遺言執行者(いごんしっこうしゃ)が主役となります。
≪ステップ1≫
遺言執行者の就任通知
遺言で指定された遺言執行者(行政書士など)は、速やかに相続人全員に対して「私が遺言を執行します」という書面を送付します。
これにより、相続人が勝手に財産を処分することを法的にブロックします。
≪ステップ2≫
財産目録の作成と報告
改めて亡くなった時点での財産を詳細に調査し、相続人に開示します。
透明性を確保することが、不信感を払拭する近道です。
≪ステップ3≫
具体的な手続きの代行
- 銀行口座の解約・払い戻し
- 有価証券の名義書換
- 不動産の名義変更(相続登記)
司法書士と連携し、義務化に対応した迅速な登記を行います。 - 遺留分に関する清算
≪ステップ4≫
業務完了報告と財産引渡し
すべての手続きが終わったことを相続人に報告し、最終的な財産を各人に引き渡して、業務が完了します。
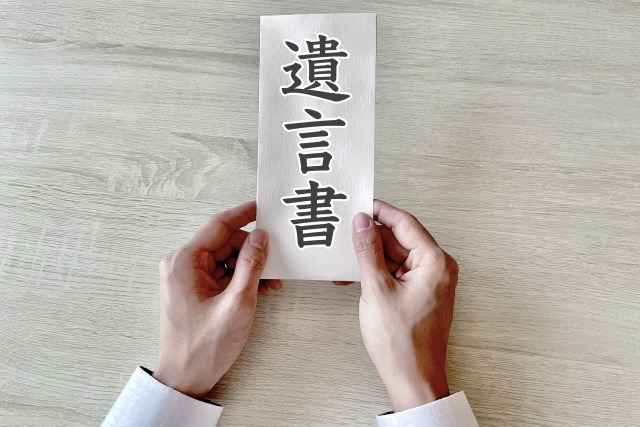
行政書士が
「一生涯のパートナー」となる理由
遺言作成において、行政書士は単なる代筆屋ではありません。
法務・実務のワンストップ対応
私たちは、遺言書の作成(文案作り)から、公証役場との調整、そして死後の執行までを一貫して引き受けます。
この「川上から川下まで」の一気通貫のサポートこそが、遺族に最大の安心感を与えます。
家族信託や任意後見との組み合わせ
シリーズ後半で解説した「家族信託」や「任意後見」を組み合わせた、より高度な生前対策の設計も可能です。
あなたの人生のステージに合わせ、最も適切な法的スキームを提案します。


よくある質問(FAQ)
正しい手順が、正しい未来を創る
遺言書作成から執行までのロードマップは、あなたの人生の総決算を美しく仕上げるための地図です。
- 事前調査(財産・戸籍・不動産地番)の精度が、遺言書の有効性を左右する。
- 2025年最新の対策として、デジタル遺産の特定と管理方法を盛り込むことが不可欠。
- 公正証書遺言は、証人の確保から公証人との調整までプロに任せるのが最も確実。
- 作成後の定期的な見直しが、最新の法改正や状況の変化から家族を守る。
- 相続登記の義務化に即応するため、不動産条項は正確な登記簿表記で行う。
- 遺言執行者を指定しておくことで、死後の煩雑な手続きを家族に代わってプロが完遂する。
遺言書は、単なる法的な書類ではありません。
それは、あなたがこれまで歩んできた人生への誇りと、これからを生きる家族への深い愛情を、確かな「形」にしたものです。
正しいプロセスを踏むことで、その想いは摩擦なく次世代へと受け継がれます。
「何から手をつければいいのか分からない」という不安は、正しい知識と、共に歩むパートナーがいれば解消できます。
あなたが描く未来の地図を、私たちと一緒に完成させましょう。
ロードマップ解説にお付き合いいただきありがとうございました。
これまでのブログを通じて、遺言の重要性と、それを支える法的な仕組みについてご理解いただけたなら幸いです。
あなたの「想い」が、世代を超えて美しく受け継がれるその日まで。
私たちは、あなたの頼れるパートナーとして、常に最前線でサポートを続けます。
ご希望に合わせて、このロードマップに基づいた初回無料診断を実施することも可能です。
