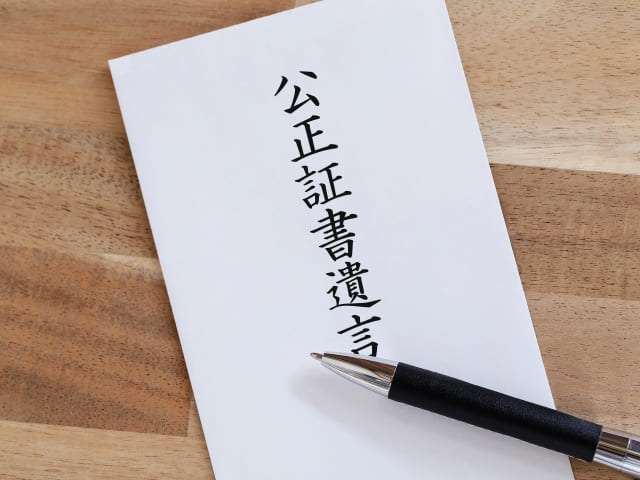※本ページはプロモーションが含まれています。
「タダより高いものはない」は遺言書にも当てはまる?
「遺言書なんて、紙とペンがあれば自分で書ける。わざわざ公証役場にお金を払うのはもったいない」
そう考える方は少なくありません。確かに、自筆証書遺言(自分で書く遺言)は、最も手軽でコストのかからない方法です。
しかし、いざ相続が発生したとき、その一通の紙が原因で家族が泥沼の争いに発展したり、結局法的に無効となって数倍の費用がかかったりするケースが後を絶ちません。
2024年4月の相続登記義務化により、不動産の名義変更を「速やかに、かつ確実に行う」ことの重要性がこれまで以上に高まりました。
遺言書は、形式不備が一つあるだけで、その役割を全く果たせなくなる非常にデリケートな書類です。
今回は、行政書士の視点から、自筆証書遺言と公正証書遺言の「本当のコスト」を算出します。
法務局の保管制度を利用した場合のメリットや、2025年現在の最新法令に基づいた選び方の基準を解説します。
自筆証書遺言の現状と「安さ」の正体
自筆証書遺言は、2020年の民法改正以降、利便性が大きく向上しました。
改正法で緩和された作成ルール
かつては全文を自筆しなければなりませんでしたが、現在は「財産目録」の部分についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められています。
これにより、多くの財産を持つ方でも作成のハードルが下がりました。
目に見えるコストは「0円」から
自分で紙に書き、自宅の金庫などに保管しておけば、作成時のコストは実質ゼロです。
この「安さ」こそが最大の魅力ですが、そこには「検認(けんにん)」という、死後の大きなハードルが隠されています。
自宅保管のリスクと「検認」の負担
法務局に預けない自筆証書遺言の場合、死後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
- 手間と時間
相続人全員に通知が行き、裁判所に集合する必要があります。
数ヶ月の時間がかかることも珍しくありません。 - 費用の発生
検認のための戸籍収集費用や、弁護士・司法書士等への依頼費用が発生し、結局、公正証書遺言よりも高額になるケースがあります。
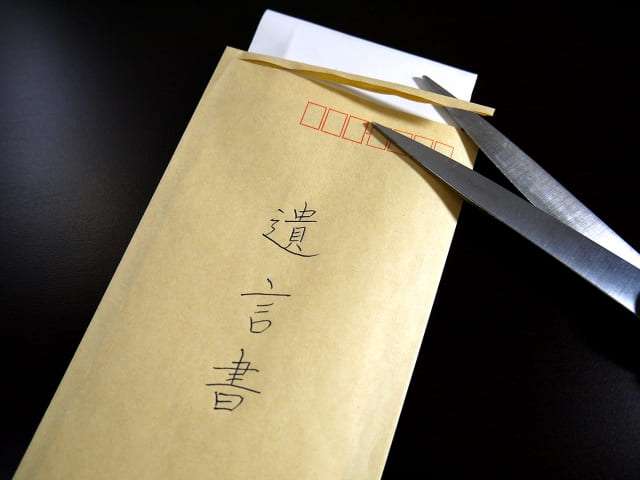
法務局の
「遺言書保管制度」は救世主か?
2020年から始まったこの制度により、自筆証書遺言の弱点が一部克服されました。
保管制度を利用するメリット
- 検認が不要
法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが免除されます。
死後、すぐに名義変更手続きに入れます。 - 紛失・改ざんの防止
国家機関である法務局が原本を保管するため、シュレッダーにかけられたり、内容を書き換えられたりする心配がありません。 - 死亡通知機能
遺言者が亡くなった際、法務局が指定された受取人に通知を送ってくれるサービスがあります。
保管制度のコスト(2025年現在)
保管手数料は3,900円です。
この金額で「紛失リスク」と「検認の手間」を解消できるのは、非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。

公正証書遺言の「安心」は
いくらで買えるのか?
公正証書遺言は、公証役場で公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)が作成する遺言書です。
公正証書遺言の圧倒的なメリット
- 形式不備による無効がない
プロが作成するため、法律上の形式ミスで無効になることはまずありません。 - 原本が公証役場に保管される
震災や火災でも、データと原本が守られます。 - 即座に執行可能
死後、検認なしにすぐ銀行や法務局で手続きができます。 - 判断能力の証明
公証人が本人と面談して作成するため、後から「認知症で書けるはずがない」といった無効主張を退ける強力な証拠になります。
公証人手数料の目安
(日本公証人連合会の規定)
手数料は「財産の額」に応じて決まります。
(税務的な計算ではなく、あくまで手数料規定に基づきます)
- 500万円以下:11,000円
- 1,000万円以下:17,000円
- 3,000万円以下:23,000円
- 5,000万円以下:29,000円
※相続人ごとに加算される仕組みがあるため、実際にはこれに数万円が加わります。
一見高く見えますが、死後のトラブル防止費用と考えれば、「最も安い保険」とも言えます。
相続登記義務化が変えた
「遺言書の選び方」
2024年4月から始まった相続登記の義務化は、遺言書選びに大きな影響を与えています。
「3年以内」の期限を守れるか
不動産の相続を知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。
自筆証書遺言で「検認」に手間取ったり、内容の不備で法務局に受理されなかったりしている間に、この3年の期限はあっという間に近づいてきます。
単独申請の確実性
公正証書遺言であれば、不動産の特定が正確になされているため、後継者が単独で迷わず、かつ迅速に登記申請を行うことができます。
このスピード感こそが、現代の相続において最も重視されるべきポイントです。

行政書士が分析する
「本当のコスト比較表」
作成時の費用だけでなく、死後の手続きまで含めたトータルコストを比較してみましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆(法務局保管) | 公正証書遺言 |
| 作成時費用 | 0円 | 3,900円 | 数万円~(財産額による) |
|---|---|---|---|
| 証人の必要性 | 不要 | 不要 | 2名必要(実費あり) |
| 死後の検認 | 必要(数ヶ月かかる) | 不要 | 不要 |
| 執行のスピード | 遅い | 早い | 最も早い |
| 紛争回避力 | 低い | 中程度 | 極めて高い |
| トータルコスト | 実は高くなるリスク大 | バランスが良い | 価値に見合った投資 |
行政書士が提案する
「賢い遺言」の作り方
私たちは、単に書類を作るだけでなく、あなたの状況に合わせた最適なプランを提示します。
≪ケースA≫
財産がシンプルで、まずは意思を残したい
法務局の「遺言書保管制度」を活用した自筆証書遺言を推奨します。
行政書士が文案を作成し、法務局での予約や手続きのアドバイスを行うことで、低コストながら確実性の高い遺言書が完成します。
≪ケースB≫
不動産、株式、事業用資産がある
迷わず「公正証書遺言」を推奨します。
特に経営者の方は、死後に数ヶ月も資産が凍結される(検認を待つ)ことは、事業の破滅を意味します。
公証人、司法書士、そして行政書士が連携して作成する「鉄壁の遺言書」こそが、事業承継の鍵となります。
≪ケースC≫
親族間に不穏な空気がある
これも公正証書遺言一択です。
公証人という公的な第三者が関与している事実は、不満を持つ相続人に対する強力な抑止力になります。
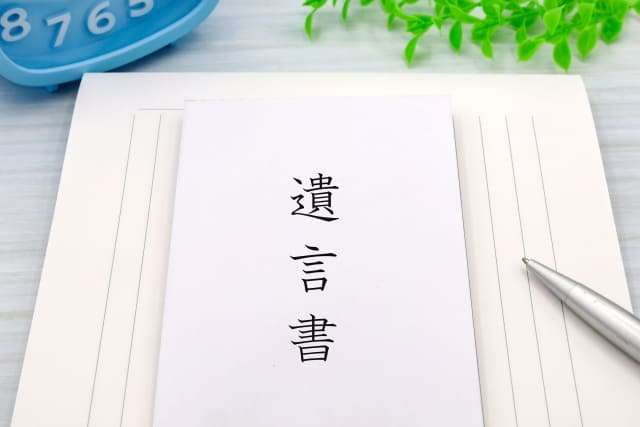
遺言書作成の失敗事例から学ぶ
遺言書作成において、ありがちで残念な失敗例を紹介します。
≪事例1≫
住所を書いてしまった自筆証書遺言
「自宅(〇〇市〇丁目〇番)」と書いた自筆遺言。
しかし、登記上の表記(地番)と異なっていたため、法務局で名義変更を拒否されました。
結局、相続人全員の判子が必要になり、遺言書を書いた意味がなくなってしまいました。
≪事例2≫
証人が見つからない公正証書遺言
「自分で公証役場に行ったけれど、証人2人を用意できずに断念した」というケースです。
行政書士にご依頼いただければ、守秘義務のあるプロが証人を務めるため、プライバシーを守りつつスムーズに作成できます。
よくある質問(FAQ)
コスト以上に
「家族の未来」を基準に選ぶ
遺言書を作成する目的は、お金を節約することではなく、あなたの死後に家族が困らないようにすることのはずです。
- 自筆証書遺言は作成コストは低いが、死後の「検認」に時間と費用がかかるリスクがある。
- 法務局の保管制度を利用すれば、自筆でも紛失リスクがなく、検認も不要になる。
- 公正証書遺言は作成費用がかかるが、形式不備による無効がなく、相続登記義務化への対応も最も迅速。
- 財産が多岐にわたる場合や、親族間の紛争が予想される場合は、公正証書が唯一の選択肢。
- 2024年からの法改正により、遺言書の「正確性」と「手続きの速さ」の価値が劇的に高まった。
- 行政書士は、予算と目的に合わせて、「自筆+法務局保管」か「公正証書」かの最適な判断をサポートする。
どの形式が「得」なのかは、あなたの財産状況や家族構成、そして「何を一番に守りたいか」によって変わります。
目先の数万円を惜しんだために、数千万円の資産が凍結され、家族が一生の不仲になるのは、あまりにも悲しいことです。
私たちは、あなたの想いを最も確実に届けるための「最適解」を一緒に考えます。
まずは、あなたの家族構成と、今感じている不安を聴かせてください。そこから、最適な遺言の形が見えてくるはずです。
あなたの決断が、大切な家族の平穏な未来を創ります。その大切な第一歩を、私たちが全力で支えます。