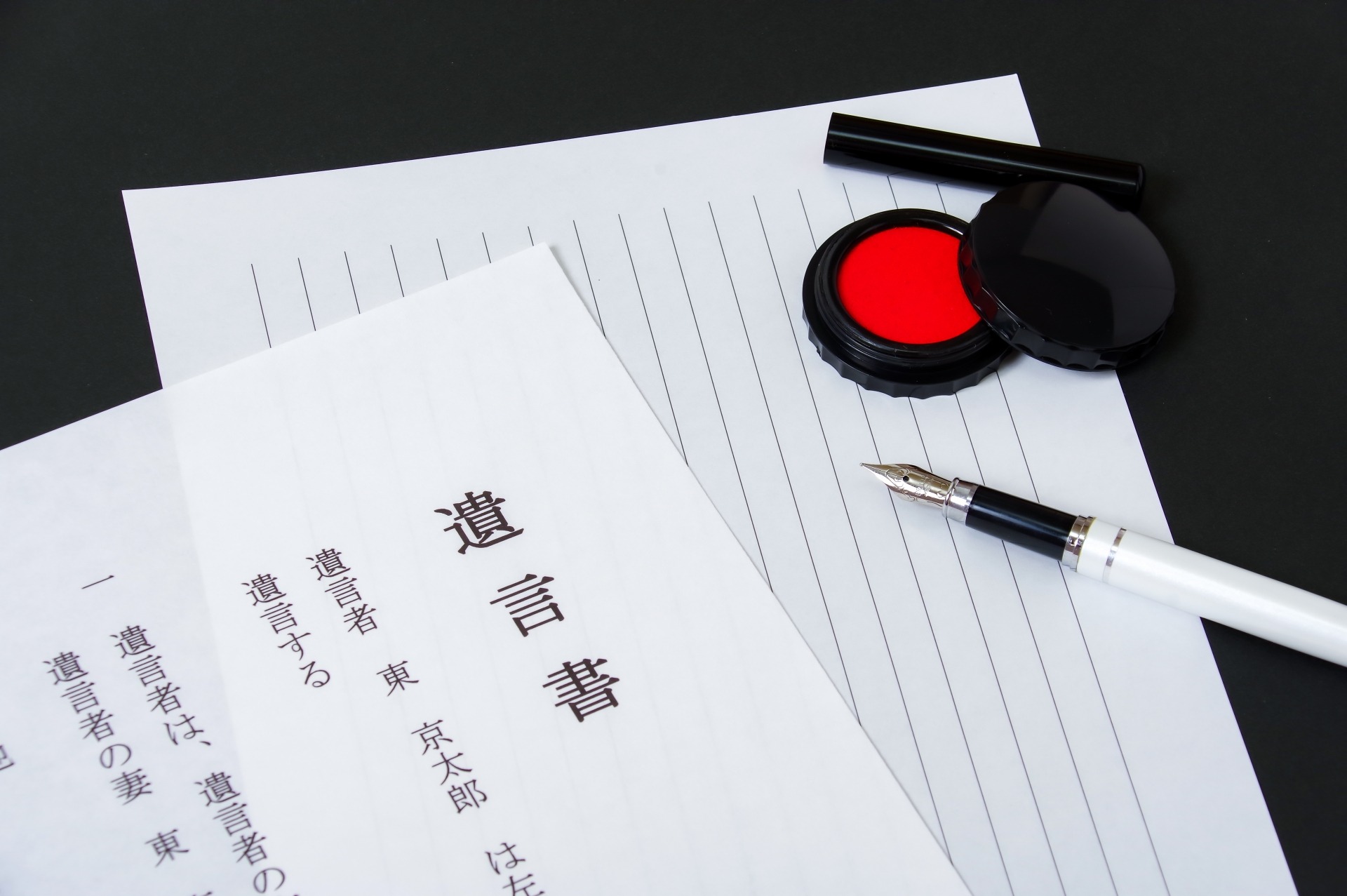※本ページはプロモーションが含まれています。
遺言書は「一生もの」ではありません
「数年前に遺言書を書いたから、もう安心だ」 もしあなたがそう思っているなら、少しだけ立ち止まって考えてみてください。
遺言書を書いてから今日までの間に、あなたの財産状況は変わっていませんか?
ご家族の状況や、あなた自身の考えに変化はありませんでしたか?
そして何より、日本の法律(民法や税法)が変わったことをご存じでしょうか。
遺言書は、作成した時点での「最適解」です。
しかし、時間が経てばその正解は変化します。
内容が古くなった遺言書は、かえって遺族を混乱させ、最悪の場合は「名義変更ができない」「多額の税金がかかる」といったトラブルを招くこともあります。
今回は、行政書士の視点から、遺言書の定期的なメンテナンスの重要性、書き直すべき5つのタイミング、そして現代特有のニーズである「おひとり様の相続」「ペットへの遺贈」「社会貢献寄付」といった発展的な活用法について解説します。
2024年から始まった「相続登記の義務化」など、最新のルールに適合した「生きた遺言書」を維持するための秘訣をお伝えします。
「一度書いたら終わり」が招く
3つの悲劇
なぜ遺言書を放置してはいけないのか。
まずは、メンテナンスを怠った場合に起こりうる具体的なリスクを見ていきましょう。
≪リスク1≫
記載された財産が「既にない」場合の混乱
遺言書に「A銀行の預金を長男に、B市の土地を次男に」と書いていても、その後、老人ホームの入居資金のためにB市の土地を売却してしまったらどうなるでしょうか。
この場合、次男への遺言部分は「撤回」されたものとみなされます。
結果として、長男は予定通り預金を受け取れますが、次男は何も受け取れず、兄弟間に深刻な感情的対立が生まれることになります。
≪リスク2≫
最新法改正に対応できず手続きが停滞する
2024年4月より「相続登記の義務化」が開始されました。
これに伴い、古い遺言書の記載内容では法務局での登記手続きがスムーズに通らない、あるいは追加の書類作成を求められるケースが増えています。
また、以前解説した「遺留分」のルールも2019年に大きく変わっており、古い知識のまま作成された遺言書は、現在の法律では「実現不可能な内容」になっている恐れがあります。
≪リスク3≫
相続税の優遇措置が受けられない
税制は毎年変わります。
例えば、配偶者の居住権を守る「配偶者居住権」の活用や、小規模宅地の特例など、作成時にはなかった有利な税制が現在は存在するかもしれません。
古い遺言書の通りに相続を発生させると、本来払わなくて済んだはずの税金を数百万円単位で支払うことになるケースもあります。
遺言書を「書き直すべき」
5つのタイミング
遺言書の鮮度を保つために、以下のライフイベントが発生した時は必ず内容を再確認しましょう。
① 家族構成に変化があったとき
- 子が結婚した、孫が生まれた。
- 相続人になるはずだった人が亡くなった(推定相続人の死亡)。
- 離婚や再婚をした。
特に、「予備的遺言(受取人が先に亡くなった場合の指定)」を書いていない場合、相続人の死亡は遺言書そのものの無効に直結します。
② 大きな財産の増減があったとき
- 不動産を売却した、または新しく購入した。
- 多額の保険金を受け取った、あるいは株価が暴落した。
- 自宅を建て替えた。
財産目録に載っている資産と、実際の資産に大きなズレが生じると、遺産分割のバランスが崩れ、遺留分トラブルの原因になります。
③ 相続税法や民法の改正があったとき
先述の通り、相続に関わる法律は非常に頻繁にアップデートされます。
「遺留分の金銭債権化(2019年)」
「自筆証書遺言の保管制度(2020年)」
「相続登記の義務化(2024年)」
など、ここ数年だけでも重要な改正が目白押しです。
④ 自身の想いや人間関係が変わったとき
「以前はお世話になった親戚に遺贈するつもりだったが、疎遠になった」「長年寄り添ってくれた長女の夫にも財産を分けてあげたくなった」など、人の心は変わるものです。
遺言書はあなたの「最期の意思」ですから、現在の素直な気持ちを反映させるべきです。
⑤ 健康状態に不安を感じ始めたとき
以前も触れた通り、認知症になって判断能力を失うと、もう二度と遺言書を書くことも直すこともできなくなります。
「少し物忘れが増えてきたかな」と感じたら、それが修正できるラストチャンスかもしれません。

【ケース別】現代のニーズに応える
発展的遺言の活用術
ここからは、従来のような「家族に財産を分ける」という目的を超えた、現代ならではの活用法について解説します。
① 「おひとり様」の相続対策
(死後事務委任との併用)
結婚していない、あるいは子供がいない「おひとり様」にとって、遺言書は家族がいる方以上に重要です。
- 誰に遺すか
兄弟姉妹がいない場合、遺言書がないと財産は最終的に国庫に帰属してしまいます。
お世話になった友人や、姪・甥、あるいは後述する寄付など、自分の意志で「出口」を決める必要があります。 - 死後事務委任契約とのセット
遺言書では「財産の行方」は決められますが、「葬儀、納骨、遺品整理、公共料金の解約」などの事務作業までは強制できません。
行政書士などの専門家と「死後事務委任契約」を並行して結んでおくことで、孤独死や無縁仏になるリスクを回避できます。
② 愛する「ペット」のための遺言
(負担付遺贈・信託)
「自分が死んだ後、残された犬や猫はどうなるのか」 これは多くの愛犬家・愛猫家にとって切実な問題です。
法律上、動物は「物」として扱われるため、直接財産を相続させることはできません。
そこで以下の手法をとります。
- 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
「ペットの世話を最期までみることを条件に、財産を〇〇さんに遺贈する」と遺言に書く方法です。 - ペット信託
より確実性を高めるため、ペットの飼育費用を信託財産として分け、第三者が飼育状況をチェックする仕組みです。
行政書士は、こうした複雑な条件付きの契約書作成を得意としています。
③ 社会への恩返し
(遺贈寄付)
近年、自分の財産を大学やNPO団体、自治体などに寄付する「遺贈寄付」を選択する方が増えています。
- 全額寄付だけでなく、「子供たちに半分、残りをユニセフに」といった指定も可能です。
- 寄付先によっては、相続税の非課税措置が受けられるメリットもあります。
- ただし、ここでも「家族の遺留分」を侵害しないよう、慎重な設計が求められます。
遺言書を書き直すための「法的ルール」
遺言書の内容を変更する方法は、法律で厳格に決まっています。
自筆証書遺言を直す場合
部分的な訂正(加筆、削除、変更)は可能ですが、「訂正箇所に印を押し、どこをどう直したか余白に記載し、署名する」という極めて面倒なルールがあります。
一箇所でも間違えると、訂正自体が無効になります。
実務上は、古い遺言書を破棄して、「全文を書き直す」のが最も安全です。
公正証書遺言を直す場合
公正証書遺言を、後から書いた自筆証書遺言で上書きすることは法的に可能です。
しかし、証拠能力の強さを考えると、やはり公正証書で作り直すのがベストです。
以前作成した役場でなくても手続きは可能で、その際に「〇年〇月〇日作成の遺言をすべて撤回し、以下の通り遺言する」と記載します。
「どちらが有効?」のルール
複数の遺言書が見つかった場合、日付が古いものと新しいもので内容が抵触する(矛盾する)部分は、「日付が新しいもの」が優先されます。
ただし、混乱を避けるためにも、書き直す際には古い遺言書を物理的に破棄するか、新しい遺言書の中で古いものを撤回する旨を明記するのが鉄則です。
「家族のパートナーとして」
行政書士の活用メリット
遺言書は、作って終わりではありません。
私たちは、あなたの人生の伴走者として、以下のようなサポートを提供します。
定期的な「遺言ドック」の実施
当事務所では、1年〜数年に一度、作成した遺言書の内容と現状にズレがないかを確認する「遺言メンテナンス(ドック)」を推奨しています。
健康診断を受けるのと同じように、遺言書も定期的な検診が必要です。
複雑な人間関係の調整とアドバイス
「後妻と前妻の子がいる」「独身の兄の将来が心配」など、家族の形は千差万別です。
行政書士は守秘義務を持つ専門家として、第三者の立場から、感情論に流されない「法的に守られた円満な解決策」を提示します。
相続を見据えたトータルコーディネート
2024年からの登記義務化に対応し、不動産をお持ちの方には、将来の相続人が困らないための記載方法をアドバイスします。
また、提携する税理士や司法書士とチームを組み、「名義変更がスムーズで、かつ税金も抑えられる遺言」をワンストップでプロデュースします。
よくある質問(FAQ)
遺言書はあなたの人生と共に進化する
遺言書作成ガイド、最後までお読みいただきありがとうございました。
- 遺言書は「一度書いたら終わり」ではなく、財産や家族の状況変化に合わせて定期的な見直し(メンテナンス)が必須です。
- 2024年の相続登記義務化など、最新の法改正を反映させていない遺言書は、死後の手続きで支障をきたす恐れがあります。
- ライフイベント(結婚、出生、不動産売買等)があったときは、書き換えの最適タイミングです。
- 「おひとり様」や「ペットの飼い主」など、現代特有の事情に合わせた負担付遺贈や寄付などの手法を組み合わせることで、より自分らしい終活が可能になります。
- 形式不備を防ぎ、確実に想いを届けるためには、公正証書遺言での作成・修正が最も推奨されます。
- 行政書士を長期的なパートナーとして活用し、数年おきに内容をチェックすることで、常に「最新の安心」を維持できます。
遺言書は、あなたが家族や大切な存在へ贈る、いわば「未来への招待状」です。
その招待状が、時代遅れの内容になっていたり、受け取った人を困らせるものになっていたりしては、せっかくの想いが台無しです。
今日、この記事を読み終えた瞬間から、あなたの「相続対策」の第二章が始まります。
既に作成済みの方も、これからの方も、まずは一度「今の自分」に最適な形は何か、私と一緒に考えてみませんか?
専門家の知識と、あなたの温かい想いを掛け合わせることで、何年経っても色あせない、最高の遺言書を完成させましょう。
あなたの人生が、そして残された方々の未来が、遺言書という一枚の紙によってより輝かしいものになることを、心より願っております。