※本ページはプロモーションが含まれています。
「家族」の形が変わっても、日本の民法は「籍」にこだわり続ける
「20年以上連れ添ってきたが、あえて籍は入れていない(事実婚)」
「同性パートナーとして共に生活を築いてきたが、万が一のときに相手はどうなるのか」
「自治体のパートナーシップ証明書は持っているが、それだけで相続は大丈夫か」
行政書士として相談を受ける中で、2025年現在、こうした「法律上の婚姻関係にないカップル」からの切実な不安が、これまでにないほど表面化しています。
多様な生き方が尊重される社会へと変化している一方で、日本の相続法(民法)の根幹は、今なお「戸籍上のつながり」に依存したままです。
厳しい現実を最初にお伝えしなければなりません。
日本の法律では、どれほど深く愛し合い、長年人生を共にしてきたパートナーであっても、戸籍上の配偶者でなければ相続権は「ゼロ」です。
何の対策もせずに一方が亡くなった場合、二人の思い出が詰まった自宅も、共に築いた預貯金も、全ては疎遠な親族の元へと渡ってしまいます。
2024年4月から施行された相続登記の義務化は、こうした「籍に入らないパートナー」にとって、さらに厳しいハードルを突きつけています。
今回は、法律の隙間で立ち往生しないために、パートナーを守るための「遺言書」を中心とした法的防衛策を解説します。
「遺言書」がないとパートナーは、
一円も受け取れない!?
日本の民法は、財産を引き継ぐべき人をあらかじめ決めています。
これを「法定相続人」と呼びますが、ここには事実婚の妻(夫)や同性パートナーは含まれません。
パートナーシップ証明書の「限界」を知る
2025年現在、多くの自治体で導入されているパートナーシップ宣誓制度。
これにより、公営住宅への入居や病院での面会などがスムーズになるケースが増えましたが、「相続権」については一切の法的効力がありません。
証明書があるからといって、銀行の解約ができるわけでも、不動産の名義を書き換えられるわけでもないのです。
親族が優先される「法定相続」の冷徹さ
あなたが亡くなった際、遺言書がなければ、財産は以下の順位で親族に引き継がれます。
- 第一順位:子供(いなければ孫)
- 第二順位:両親(いなければ祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(いなければ甥・姪)
事実婚・パートナーが直面する
「3つの悲劇」
対策を怠った結果、現場でどのようなトラブルが起きているのか。
行政書士がよく耳にする事例を紹介します。
自宅からの立ち退き要求
二人でローンを出し合って買った家、あるいは一方の名義の家で暮らしていたケースです。
名義人が亡くなった途端、相続権を得た親族(例えば亡くなった人の兄弟など)から「家を売却して現金を分けたいから、すぐに出て行ってほしい」と要求される事例が多発しています。
法律上の配偶者であれば「配偶者居住権」という守りがありますが、事実婚や同性パートナーには、この権利を当然に主張することは難しいのが現状です。
共有名義の落とし穴と「相続登記義務化」
二人の共有名義で不動産を持っている場合でも安心はできません。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、一方が亡くなった際、その持ち分は「相手」ではなく「亡くなった人の親族」に渡ります。
義務化によって放置が許されなくなったため、親族が速やかに名義変更を行い、結果として「他人(パートナーの親族)と不動産を共有する」という、売ることも貸すこともできない地獄のような状況に陥ります。
葬儀や遺品整理に介入できない
意外と知られていないのが、死後の「事務」の問題です。
遺言書がない場合、遺体の引き取りや葬儀の差配、お墓の管理などは全て「血縁者」が優先されます。
最期を看取ったパートナーが葬儀の席で隅に追いやられたり、遺品の整理すら拒否されたりするという、感情的にも極めて辛い事態が起きています。
パートナーを守るための
「遺言書」作成のポイント
パートナーに財産を遺すことを、法律用語で「遺贈(いぞう)」と呼びます。
これを確実に行うためには、自筆ではなく「公正証書遺言」を作成することが、2025年現在、強く推奨されています。
「包括遺贈」か「特定遺贈」か
- 包括遺贈(ほうかついぞう)
「財産の全部をパートナーに遺す」という書き方です。
メリットは漏れがないことですが、デメリットはパートナーが借金も含めた全ての権利義務を引き継ぎ、親族との遺産分割協議に巻き込まれる可能性があることです。 - 特定遺贈(とくていいぞう)
「自宅不動産と預金口座をパートナーに遺す」というように、財産を指定します。
親族との摩擦を最小限に抑えるには、こちらの方が実務的にはスムーズな場合があります。
「予備的遺言(よびてきいごん)」の重要性
お互いに遺言書を書き合う場合、注意が必要なのが「同時に亡くなった場合」や「一方が先に亡くなった場合」です。
「もし受遺者(パートナー)が自分より先に亡くなっていた場合は、財産を〇〇(特定の団体や親族)に寄付する」
といった予備的な指示を書いておかないと、結局最後は国庫に没収されたり、意図しない親族へ流出したりしてしまいます。
遺留分(いりゅうぶん)という名の
「最後の障害」
遺言書で「パートナーに全財産を遺す」と書いても、完全に安心はできません。
亡くなった方の親族(子供や両親)には、法律で守られた最低限の取り分である遺留分があるからです。
親族からの「現金の請求」に備える
2019年の民法改正以降、遺留分を侵害された親族は、不動産そのものではなく「現金を支払え(遺留分侵害額請求)」と主張するようになりました。
パートナーが家を相続できても、亡くなった人の親族に支払う現金を準備できなければ、結局は家を売るしかなくなります。
兄弟姉妹には遺留分がないという「救い」
唯一の救いは、亡くなった方の「兄弟姉妹(およびその子供)」には遺留分がないという点です。
もしあなたに子供がおらず、両親も既に他界している場合、遺言書さえあれば、兄弟姉妹の反対を押し切って全財産をパートナーに遺すことが可能です。
このケースこそ、遺言書の恩恵を最も受けるパターンと言えます。

遺言書とセットで検討すべき
「3つの法的契約」
パートナーとの生活を全方位で守るためには、遺言書(死後の対策)だけでなく、生前の対策も不可欠です。
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)
葬儀の喪主をパートナーに務めてもらう、お墓を管理してもらう、スマホやSNSの解約、ペットの世話などを託すための契約です。
遺言書では「財産」以外のことは強制できませんが、この契約をセットにすることで、パートナーが堂々と「喪主」や「片付けの責任者」として振る舞える法的根拠になります。

任意後見契約(にんいこうけんけいやく)
どちらかが認知症などで判断能力を失った際、パートナーを後見人に指名しておく契約です。
これがないと、裁判所によって選ばれた「赤の他人の専門家」が財産を管理することになり、パートナーであっても生活費の引き出しすら自由にできなくなる恐れがあります。

賃貸借契約・入居時の工夫
もしどちらかの名義の持ち家ではなく、賃貸住宅に住んでいる場合、名義人が亡くなった後にパートナーが住み続けられるかどうかは、大家さんとの契約や判例に左右されます。
生前に連名で契約するか、あるいは「居住権」についての合意を明確にしておくことがリスクマネジメントです。
パートナーが直面する「税金の重圧」
遺言書で財産を渡せるようになったとしても、次に立ちはだかるのが「税制上の不利」です。
「配偶者控除」が使えない痛み
法律上の配偶者であれば、1億6,000万円までの相続について税金がかからない「配偶者控除」がありますが、事実婚・パートナーにはこれが適用されません。
基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える財産がある場合、パートナーには多額の相続税が容赦なく課せられます。
相続税の「2割加算」
さらに過酷なことに、法律上の配偶者や子供・親以外の人が財産を相続する場合、算出された相続税額に20%が上乗せ(2割加算)されます。
パートナーを大切に思うなら、相続税を支払うための現金を生命保険(受取人をパートナーに指定)などで準備しておくといった、トータルな資金計画が求められます。
行政書士が
「パートナーの守り人」となる理由
事実婚や同性パートナーの遺言作成は、親族関係の調査から、遺留分の計算、そして何より「死後の親族との摩擦をどう最小限にするか」という高度な戦略が必要です。
遺言執行者に専門家を指定する
パートナーが一人で、亡くなった方の親族と対峙するのは精神的に大きな負担です。
遺言書の中で行政書士などを遺言執行者に指定しておけば、専門家が第三者の立場として、銀行手続きや不動産の名義変更を全て代行します。
パートナーは親族と直接やり取りすることなく、スムーズに財産を受け取ることができます。
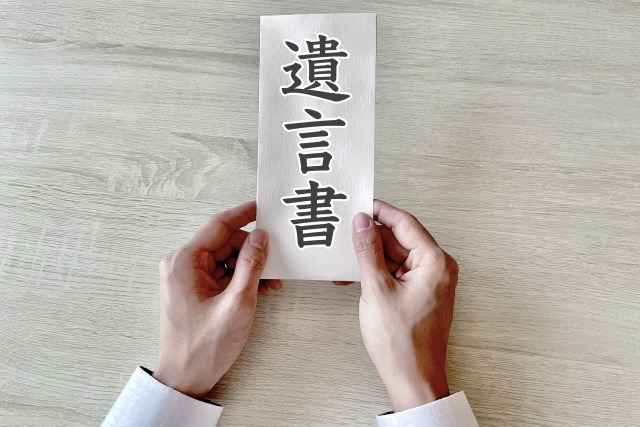
最新の裁判例と
パートナーシップ制度のアップデート
2024年から2025年にかけて、同性婚の合憲性を巡る訴訟や、犯罪被害者給付金の受給権を巡る事実婚の権利認定など、司法の判断は刻一刻と動いています。
私たちは最新の情報を踏まえ、今できる「最善の防衛ライン」を提案します。
よくある質問(FAQ)
法的保護がないからこそ、
自らの手で「盾」を作る
事実婚やパートナーシップ関係にある方々にとって、遺言書は単なる書面ではなく、大切な人の「住まい」と「生活」を守るための最後の砦です。
- 相続権ゼロの壁を越えるためには、遺言書による「遺贈」の設定が必須不可欠。
- パートナーシップ証明書は相続における法的効力を持たず、これだけでは財産を守れない。
- 相続登記義務化により、共有不動産や放置された名義がパートナーの生活を脅かすリスクが増大。
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、子供や親がいない場合は遺言書が「最強の武器」となる。
- 相続税の2割加算や配偶者控除の適用外といった税制上の不利を、生命保険等でカバーする設計が重要。
- 遺言執行者に専門家を据えることで、パートナーを親族間のトラブルから法的に守り抜く。
法律上の婚姻届を出さないという選択には、それぞれの信念や事情があるはずです。
その選択を尊重しつつ、万が一のときに相手が路頭に迷うようなことがあっては、遺されたパートナーは深い悲しみと苦労を背負うことになります。
「戸籍」という形にとらわれない新しい絆を、私たちは「法律」という形のある盾で守り抜くお手伝いをします。
あなたの大切なパートナーが将来、笑顔であなたの思い出と共に生きていけるよう、今すぐ確かな準備を始めましょう。
どのような家族の形であっても、あなたの「遺したい」という尊い想いが、国境や制度の壁を越えて確実に届くよう、私たちは専門知識を尽くしてサポートし続けます。
