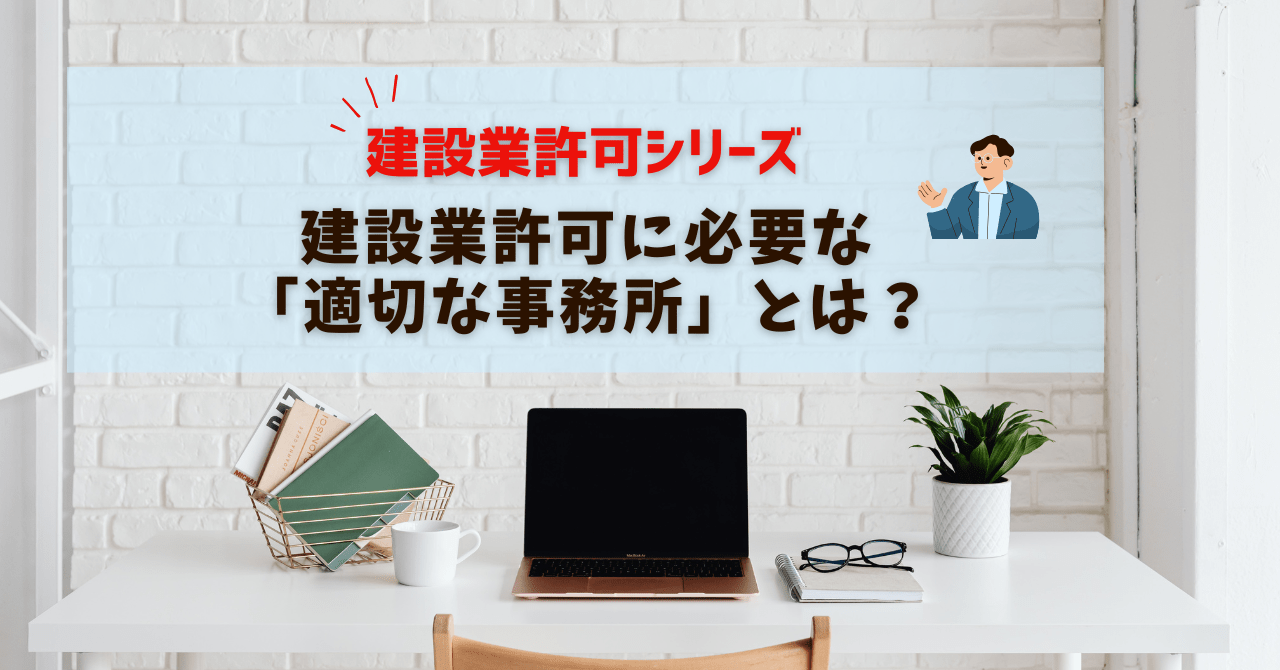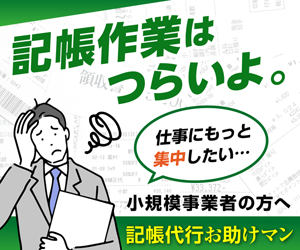※本ページはプロモーションが含まれています。
「場所」があれば良いわけではない?許可における営業所の重要性
建設業許可の申請準備を進める中で、意外な落とし穴となるのが「営業所(事務所)」の要件です。
「登記上の本店があるから大丈夫」「自宅で仕事をしているから問題ない」と考えていませんか?
実は、建設業法および東京都の審査基準において、「営業所」として認められるためには、単に住所があるだけでなく、「請負契約を締結する実体的な機能」と「独立した空間」が確保されていることが厳格に求められます。
特に東京都では、写真による詳細な確認や、場合によっては立入調査が行われることもあり、要件を満たさない「名ばかり営業所」や「住居兼用の曖昧なスペース」では許可が下りません。
この記事では、東京都の「建設業許可申請の手引」に基づき、営業所として認められるための5つの必須条件、多くの事業者が悩む「自宅兼事務所」や「レンタルオフィス」での申請可否、そして審査を一発でクリアするための「写真撮影のポイント」を、専門家である行政書士が解説します。
東京都が定める「営業所」の定義
5つの必須要件
東京都の手引において、建設業の営業所とは、単なる連絡場所や作業員の詰め所ではなく、「請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所」と定義されています 。
許可を取得するためには、以下の5つの要件(ア〜カ)をすべて満たしている必要があります 。
≪要件1≫
実体的な業務機能(来客対応と契約締結)
外部から来客を迎え入れ、その場所で建設工事の見積り、入札、契約締結などの実務を行える環境が必要です 。
≪要件2≫
独立性の確保(明確な区分け)
これが最もトラブルになりやすいポイントです。
営業所スペースは、他法人、他の個人事業主、または個人の生活空間(居住部分)とは、間仕切り等で明確に区分されていなければなりません 。
- 他社と同居の場合
同一フロアに他社がいる場合、固定式パーティションなどで天井近くまで仕切られ、出入り口が別にあるなど、独立性が保たれている必要があります。 - 自宅兼事務所の場合
リビングや寝室などの生活空間を通らずに営業所へ入れるか、または生活空間とは壁や扉で完全に遮断された専用の部屋である必要があります 。
≪要件3≫
備品の設置と通信環境
契約締結の実務を行うために必要な什器・備品が備わっていることが必須です。
≪要件4≫
常勤役員等と専任技術者の常駐
その営業所には、許可要件の核となる「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」または「令3条の使用人(支店長等)」、および「専任技術者(専技)」が常勤していなければなりません 。
≪要件5≫
看板・標識の掲示
建物の入口やポスト、ドアなどに、商号(会社名)や「建設業の営業所であること」が外部から明確に分かる看板や表札を掲示している必要があります 。
賃貸・自宅・レンタルオフィス
物件タイプ別の申請可否と注意点
「この物件で許可は取れるのか?」という疑問に対し、物件タイプ別の判断基準と注意点を解説します。
賃貸物件の場合:「使用目的」の壁
賃貸マンションやテナントビルを借りる場合、賃貸借契約書の内容が審査されます。
- 契約目的
使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所」となっている必要があります 。 - 住居専用契約の罠
契約書の目的が「住居用」となっている場合、原則として営業所とは認められません。
この場合、貸主(大家さんや管理会社)から「建設業の営業所として使用することを承諾する書面(使用承諾書)」をもらう必要があります 。
公的賃貸住宅(都営・UR等)は原則NG
都営住宅、公社住宅、UR都市機構(公団)の賃貸住宅は、その設置目的が「居住」に限定されているため、原則として営業所としての利用は認められません 。
これらの住所で登記していても、許可は下りないため、移転が必要になります。
レンタルオフィス・シェアオフィスの判断基準
近年増えているレンタルオフィスですが、許可が下りるものと下りないものが明確に分かれます。
- 許可OK
個室タイプで、天井まで壁があり、施錠ができ、専用の電話回線や表札が出せるもの。独立性が確保されているとみなされます。 - 許可NG
フリーアドレス(固定席がない)、パーティションが低い(上部が空いている)、バーチャルオフィス(住所貸しのみ) 。
これらは独立性と実体性がないため、認められません。
東京都の審査をクリアする
「営業所写真」撮影マニュアル
東京都の申請では、営業所の実態を証明するために「営業所写真」の提出が必須です。
この写真の撮り方には細かいルールがあり、不備があると再提出(再撮影)になります 。
撮影が必要な6つのアングル
手引に基づき、以下の箇所をもれなく撮影し、A4用紙に貼付して提出します 。
- 建物の全景
建物全体がわかる写真(1階から屋上まで)。ビル名などが確認できるもの。 - 建物入口
建物のメインエントランス付近。 - テナント表示(集合ポスト)
入居者一覧や集合ポストに、申請者の商号が表示されている箇所。 - 事務所の入口
営業所のドア付近。
商号(看板・表札)が掲示されていることが必須です。 - 事務所の内部(全景)
執務スペース全体が見渡せるように、複数方向から撮影します。 - 執務スペースの詳細
机、椅子、電話機、パソコン、コピー機などが設置され、業務が可能であることを示す写真。
撮影時の重要テクニックと注意点
- ブラインド・カーテン
窓がある場合は、ブラインドやカーテンを開けた状態で撮影し、そこが閉鎖的な空間でないことを示します 。 - 間仕切りの証明
他社と同居や自宅兼用の場合は、区分け(間仕切り)の状況がわかるように、境界部分を明確に撮影します 。 - 固定電話
電話機が設置されていることがわかるアップの写真もあるとベターです。

申請に必要な証明書類
所有形態別のチェックリスト
営業所の「使用権原(その場所を使う権利)」を証明するために、以下の書類が必要です 。
自己所有(自社ビル・持ち家)の場合
- 建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
- 発行後3ヶ月以内のもの。
- 申請者(法人または個人)が所有者であることが記載されていること。
- 建物が未登記の場合は、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書で代用可能です 。
賃貸物件の場合
- 賃貸借契約書の写し
- 契約期間
申請日時点で契約期間内であること(自動更新条項があれば期間切れでも可、ただし定期借家契約は要注意)。 - 使用目的
「事務所」「店舗」等になっていること。 - 貸主・借主
申請者名義で借りていること。
法人申請なのに社長個人名義で借りている場合は、別途「使用貸借契約書」等が必要になることがあります。
- 契約期間
行政書士に依頼するメリット
物件選定からの「予防法務」
営業所の要件は、契約や内装工事が終わった後に「不適合」が判明すると、移転や再工事という致命的な損害につながります。
開業前の物件診断と写真撮影代行
行政書士に依頼することで、以下のサポートが受けられます。
- 物件契約前のリーガルチェック
検討中の物件が建設業許可の要件を満たすか、賃貸借契約書の内容に問題がないかを事前に診断します。 - 使用承諾書の交渉サポート
大家さんや管理会社に提出する承諾書の文案作成や説明をサポートします。 - 写真撮影と書類作成
東京都の審査基準を熟知した行政書士が、「審査に通るアングル」で写真を撮影し、配置図(間取り図)を作成します。
この記事のまとめ
建設業許可における営業所は、単なる「住所」ではなく、建設業を営むための「城」です。
東京都知事許可を取得するためには、実体的な業務機能と独立性を確保し、それを写真と書類で客観的に証明しなければなりません。
- 東京都の営業所要件は、「請負契約の実体行為を行うこと」と「他者からの独立性」が2大原則です。
- 自宅兼事務所やレンタルオフィスでも申請は可能ですが、天井までの間仕切りや専用の出入り口など、厳しい独立性の基準をクリアする必要があります。
- 都営住宅やUR賃貸は、原則として営業所として認められません。
- 申請には、建物全景、入口(看板)、内部(執務スペース)など、指定されたアングルの写真が必須であり、ブラインドを開けるなどの細かいルールがあります。
- 賃貸物件の場合、契約書の使用目的が「住居」となっていると、貸主の使用承諾書が必要になるため、契約前の確認が不可欠です。
「とりあえず契約してから考えよう」は最も危険です。
物件選びやレイアウトの段階から、許可要件を意識した準備を進めることが、スムーズな許可取得への最短ルートとなります。
不安な場合は、契約前に必ず行政書士にご相談ください。
💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。