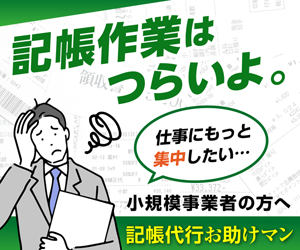※本ページはプロモーションが含まれています。
中古品ビジネスの成功と信頼性を担保する「古物商許可」
フリマアプリやネットオークションの普及、そしてSDGsへの意識の高まりにより、リユース・リサイクル市場は急速に拡大しています。
「中古品を仕入れて販売したい」、「古物のネット販売を副業として始めたい」と考える個人や法人が増える中、その活動の土台となるのが「古物商許可」です。
この許可は、単なる行政手続きではなく、盗品の流通防止を目的とした「古物営業法」に基づく、中古品を取り扱う上での社会的責任と信頼の証です。
許可なく営業した場合、古物営業法違反で処罰の対象(罰金・懲役)になるリスクがあります。
この記事では、古物営業法に精通した行政書士の視点から、古物商許可の具体的な要件、警察署(公安委員会)による審査の厳格なポイント、法人・個人で異なる必要書類、そして行政書士に依頼して最短かつ確実に許可を取得するためのロードマップを解説します。
古物商許可とは?
なぜ「継続的な販売」に許可が必須か
古物商許可は、古物営業法に基づいて、中古品などを「仕入れて販売する」事業を行う場合に、管轄の警察署を経由して公安委員会から受ける許可です。
古物に該当する物品の定義
「仕入れ」の判断基準
古物営業法でいう「古物」とは、一度使用された物品、または使用されていないが取引された物品、そしてこれらに幾分の手入れをしたものを指します。
| 分類(全13品目) | 例 |
| 衣類 | 古着、バッグ、靴、アクセサリーなど |
|---|---|
| 機械類 | 家電製品、スマホ、PC、カメラなど |
| 書籍類 | 古本、雑誌、漫画など |
| 美術品類 | 絵画、骨董品、彫刻など |
| 乗物類 | 自転車、バイク、自動車など |
「古物商許可」が必要となるのは、以下のいずれかの行為を反復・継続して行う(=事業とする)場合です。
- 中古品を買い取って販売する(リサイクルショップ、転売)
- 中古品を交換する(物々交換含む)
- 古物をレンタルする
- 中古品を修理して販売する(部品交換など高度な修理を除く)
【注意】許可が不要なケース
(不用品の個人売買)
自宅の不用品を処分目的でフリマアプリで販売する、といった「自分で使っていたものを売るだけ」の行為は、古物営業に該当しないため許可は不要です。
しかし、販売目的で中古品を仕入れ始めた時点で許可が必須となります。
古物商許可申請の具体的な要件
(警察による厳格な審査ポイント)
古物商許可申請は、警察が「この人物に古物営業を営ませて問題ないか」を審査する行政手続きです。
特に、盗品や不正品の流通を防ぐため、申請者や営業所に対して厳しい要件が課されます。
許可の3大要件
(欠格事由・営業所・管理者)
1. 欠格事由に該当しない
最も重要であり、行政書士による事前の確認が必須となるのが「欠格事由」です。
以下に該当する場合、許可は下りません。
- 過去に古物営業法や特定の刑法に違反し、刑の執行が終わってから5年を経過していない。
- 破産手続きの開始決定を受け、復権を得ていない。
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない。
- 住所が定まらない者。
行政書士は、申請者や役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)を取得し、欠格事由に該当しないことを事前に確認することで、無駄な申請を防ぎます。
2. 適切な「営業所」が確保されている
- 実体のある場所
バーチャルオフィスや「住所のみ」の貸しスペースでは認可が下りない場合があります。 - 使用権限の証明
賃貸物件の場合、管理会社や大家さんの「古物営業を行うことへの承諾書」が必要になるケースが多々あります。 - 行政書士のサポート
営業所とする物件の使用権限や使用制限(賃貸借契約書など)を事前に調査し、警察署への確認(事前相談)を推奨します。
3. 営業所ごとに「管理者」を選任している
≪管理者≫
営業所ごとに、古物取引に関する責任者(管理者)を必ず選任しなければなりません。
これは欠格事由に該当しない人物でなければならず、原則、常勤できる者である必要があります。

ネット販売(非対面取引)特有の注意点
実店舗がない場合でも、ネットショップ(BASE、Shopify、Amazonなど)やフリマサイト、SNSでの販売を継続的に行う場合は許可が必要です。
- サイトURLの記載
申請書には、使用するウェブサイトのURLを全て正確に記載し、その画面コピーの提出が求められます。 - プロバイダ情報の開示
URLの使用権限を証明するため、プロバイダ等からの証明書や契約書の写しが必要になることがあります。
行政書士による古物商許可申請サポート具体的な流れとメリット
古物商許可の申請は、必要書類の種類が多く、平日の日中に警察署に複数回足を運ぶ必要があるため、本業が忙しい個人事業主や法人にとって大きな負担となります。
行政書士が代行できる主な業務内容
行政書士は、古物営業法に基づく各種手続きのプロフェッショナルです。
- 要件確認・ヒアリング
欠格事由や営業所の適格性など、許可要件の事前確認を徹底し、申請可否を判断します。 - 書類収集の支援・代行
住民票、登記事項証明書、身分証明書など、市区町村役場や法務局で取得が必要な書類の案内や取得代行を行います。 - 申請書・添付書類の作成
複雑な略歴書や、法人特有の定款チェック、申請書の正確な作成を行います。 - 警察署への提出代行
管轄警察署への提出を代行(または同行)することで、申請者の時間と手間を大幅に削減します。
行政書士に依頼する4つの実質的メリット
| メリット | 具体的な効果 |
| コンプライアンスの徹底 | 許可がないまま営業するリスク(古物営業法違反)を回避し、法令遵守を徹底できます。 |
|---|---|
| 時間と手間の削減 | 警察署との事前相談や書類の収集・作成に時間をかけずに、本業の準備に集中できます。 |
| 不備による遅延の防止 | 専門家によるチェックで書類の不備・不足を防ぎ、スムーズな許可取得を実現します。 |
| 許可取得後のフォロー | 許可後の古物台帳の記録義務、標識の掲示義務、変更届の提出など、継続的な義務についても助言や代行が可能です。 |
許可取得後の重要義務
「古物台帳・標識掲示」と法改正対応
古物商許可は取得がゴールではありません。盗品等の流通防止という法の目的に従い、古物商にはさまざまな義務が課されます。
古物商に課せられる3つの主要義務
- 古物台帳の記録・保存義務
取引の内容(日付、古物の品目、特徴、取引相手の住所・氏名、確認方法など)を正確に帳簿に記録し、3年間保存する義務があります。 - 確認義務の徹底
古物を買い取る際、相手の身分証明書等を確認し、不正品の疑いがある場合は直ちに警察へ通報する義務があります。 - 標識(プレート)の掲示義務
営業所には「古物商プレート」を、ネットショップには「氏名または名称」「許可をした公安委員会の名称」「許可番号」などを表示する義務があります。
法改正への対応:古物商は常に変化する
古物営業法は、時代の変化(特にインターネット取引の増加)に伴い改正されることがあります。
例えば、令和2年には「非対面取引における確認方法」に関する改正がありました。
行政書士は、これらの最新の法令情報に基づいたアドバイスを提供し、お客様の営業活動が常に適法であることをサポートします。
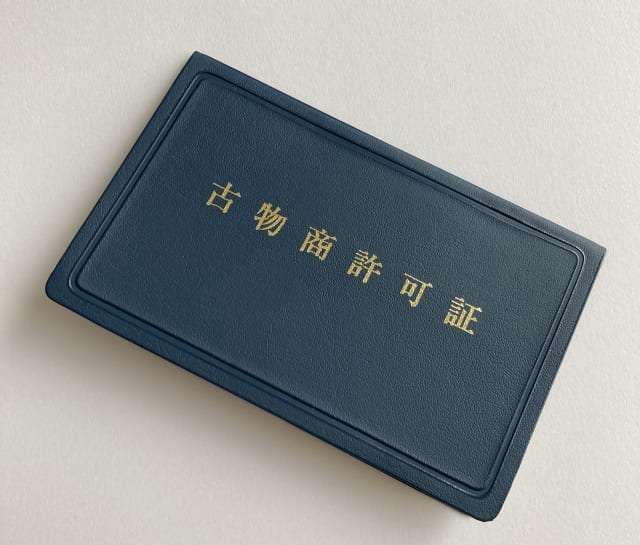
この記事のまとめ
中古品販売ビジネスを始めるなら、古物商許可は必須の第一歩であり、事業を法的なリスクから守るための「信頼と安全のパスポート」です。
許可がないまま営業した場合、古物営業法違反で処罰の対象になることもあります。
- 古物商許可は、中古品を仕入れて販売する事業を行う場合、実店舗・ネット販売を問わず必須です。
- 許可審査では、欠格事由への非該当、適切な営業所の確保、管理者選任の3大要件が厳しくチェックされます。
- 法人・個人ともに、住民票、身分証明書、略歴書、登記事項証明書など多岐にわたる公的書類の提出が求められます。
- 行政書士は、書類の収集・作成代行、警察署との折衝、欠格事由の事前確認により、申請者の時間と労力を削減し、スムーズな許可取得を支援します。
- 許可取得後も、古物台帳の記録・保存や標識の掲示など、法令遵守の義務が継続します。
古物商許可の取得は、煩雑な書類と警察とのやり取りが必要なため、「中古品販売を始めたいが手続きに自信がない」、「自分に許可が取れるのか知りたい」と感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。
私たちは、お客様が安心して本業に集中できるよう、開業前の法的土台作りを徹底的にサポートいたします。
💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。