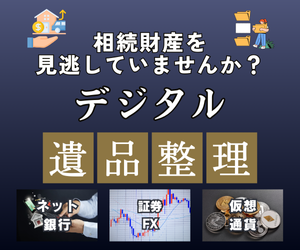※本ページはプロモーションが含まれています。
「昔亡くなった祖父名義の土地、放置していても大丈夫?」
「2024年から登記が義務化されたと聞いたけれど、具体的に何をすればいい?」
「名義変更をしないと10万円の罰金がかかるって本当?」
これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年(令和6年)4月1日から法律によって義務化されました。
2025年現在、この制度はすでに本格運用されており、法務局の運用も厳格化しています。
不動産の名義変更を放置することは、単なる手続き漏れに留まらず、過料(罰金)の対象となるだけでなく、次世代への「負の遺産」となりかねません。
しかし、登記の手続きは複雑で、どこから手を付ければよいか戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、中野区で相続書類作成をする行政書士が、最新の改正法と実務データに基づき、相続登記義務化の全貌と、トラブルを避けるための準備手順を解説します。
なぜ「相続登記」が義務化されたのか?
背景にある社会問題
そもそも、なぜ国は今まで任意だった登記を義務化したのでしょうか。
その背景には、日本全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。
「所有者不明土地」の現状
国土交通省の調査や有識者会議の推計によると、日本国内において所有者が不明、あるいは連絡がつかない土地の面積は、九州全体の面積を上回る約410万ヘクタールに達すると言われています。
これにより、公共事業が進まない、災害復旧が遅れる、空き家が放置され治安が悪化するといった実害が多発しています。
経済的損失の大きさ
所有者不明土地問題による経済的損失は、2040年までになんと約6兆円にのぼると試算されています。
この状況を打破するため、民法および不動産登記法が改正され、相続登記の義務化という強力なルールが敷かれることになりました。
義務化の内容と「3つの重要ルール」
義務化の内容は非常に具体的です。
以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。
① 申請期限は「3年以内」
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
② 過去の相続分も対象(遡及適用)
ここが最も注意すべき点です。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象となります。
放置されていた古い名義の土地がある場合、猶予期間(2027年3月31日まで)の間に登記を済ませる必要があります。
③ 10万円以下の過料(罰則)
正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される可能性があります。
これは「知らなかった」では済まされない公的なペナルティです。
手続きが間に合わない時の救済措置
「相続人申告登記」
「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が多すぎて連絡がつかない」といった理由で、3年以内の期限を守れないケースも想定されます。
そのために新設されたのが「相続人申告登記」という制度です。
相続人申告登記のメリット
- 簡易的な届出
相続人が自分一人だけで、自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易的な手続きです。 - 義務の履行とみなされる
これを行うことで、3年以内の申請義務を果たしたものとみなされ、過料を免れることができます。 - 戸籍の範囲が狭い
通常の相続登記(出生から死亡まで)よりも少ない戸籍で手続きが可能です。
注意点
ただし、これはあくまで「暫定的な届出」に過ぎません。
不動産を正式に売却したり、担保に入れたりするためには、最終的に遺産分割を終えて正式な相続登記をする必要があります。
登記申請までの
「一般的な流れ」と準備書類
実際の登記申請(オンラインまたは書面提出)は専門資格である司法書士の業務ですが、そこに至るまでの「書類準備」は共通のプロセスです。
必要な書類のリスト
相続登記を完了させるためには、以下の書類を揃えるのが一般的です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本および住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の算出に必要)
≪ステップ1≫
不動産の特定(財産調査)
まずは「名寄帳」などを取得し、登記すべき不動産を漏れなくリストアップします。
≪ステップ2≫
相続人の特定(戸籍収集)
古い戸籍を遡り、誰が法定相続人であるかを確定させます。
≪ステップ3≫
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するかを決定し、協議書を作成します。
≪ステップ4≫
登記申請
これら全ての書類を法務局に提出します。
この最終ステップにおいて、専門家に代理を依頼する場合は司法書士がその役割を担います。
行政書士が「登記準備」において
果たす重要な役割
行政書士は、登記申請そのもの(法務局へのオンライン申請等)を行うことはできませんが、登記の「前段階」である複雑な事務作業において、皆様を強力にサポートします。
複雑な「戸籍収集」のプロ
明治・大正時代の難解な戸籍を解読し、全国の役所から書類を揃える作業は、行政書士の得意分野です。
法務局でそのまま使える「法定相続情報一覧図」の作成も代行します。
「遺産分割協議書」の作成
「誰が不動産を継ぐか」という合意内容を、法務局で差し戻されない正確な文言で書面にまとめます。
これは、登記の「原因証書」となる極めて重要な書類です。
司法書士との連携(橋渡し)
当事務所では、信頼できる司法書士と連携しております。
行政書士が書類を完璧に整えた上で司法書士に引き継ぐことで、お客様は窓口を一本化でき、スムーズに登記を完了させることが可能です。
「住所・氏名の変更登記」も義務化へ
不動産に関連して、もう一つ重要な法改正があります。
2026年(令和8年)4月までには、「住所や氏名の変更登記」も義務化されることが決まっています。
- 内容
引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、その日から2年以内に変更登記をしなければなりません。 - 罰則
5万円以下の過料。
「相続登記」だけでなく、今後は「不動産の名義人の情報は常に最新にしておく」ことが国民の義務となります。
よくある質問と回答
今すぐ動き出すべき理由
相続登記の義務化は、もはや避けては通れない法的ルールです。
2025年は、過去の未登記分を解消するための「猶予期間」の真っ只中にあります。
- 相続登記は、不動産取得を知った日から「3年以内」に行うことが法律で義務付けられた
- 過去の相続分も対象であり、放置すると最大10万円の過料が課される可能性がある
- 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で一時的に義務を回避できる
- 登記申請には、出生から死亡までの戸籍など、膨大な書類準備が必要である
- 実際の登記申請は自分で行うか、司法書士に依頼する必要がある
- 行政書士は、登記に必要な「戸籍収集」「遺産分割協議書作成」の段階で大きな力となる
- 2026年には「住所変更登記」の義務化も控えており、不動産管理の意識向上が求められる
相続登記を完了させることは、ご自身の権利を守るだけでなく、大切な不動産を「負動産」にしないための家族への最大の配慮です。
中野区のかとう行政書士事務所では、登記の「準備段階」である戸籍調査、不動産名義の確認、そして遺産分割協議書の作成をトータルでサポートしております。
複雑な書類集めや、疎遠な相続人との連絡調整など、一般の方がつまずきやすいポイントをプロの知見で解決します。
当事務所が書類を完璧に整え、提携する司法書士へバトンタッチすることで、皆様の負担を最小限に抑えた名義変更を実現します。
まずは、お手元にある古い権利証や納税通知書を一通お持ちください。
そこから、皆様の大切な財産を守るための道筋を共に描いていきましょう。
お問い合わせは、お電話または24時間対応のフォームより心よりお待ちしております。
正しい手続きを迅速に終えることが、家族の未来に大きな安心をもたらします。
私たちは、そのための確かなパートナーとして、一歩一歩誠実にお手伝いいたします。