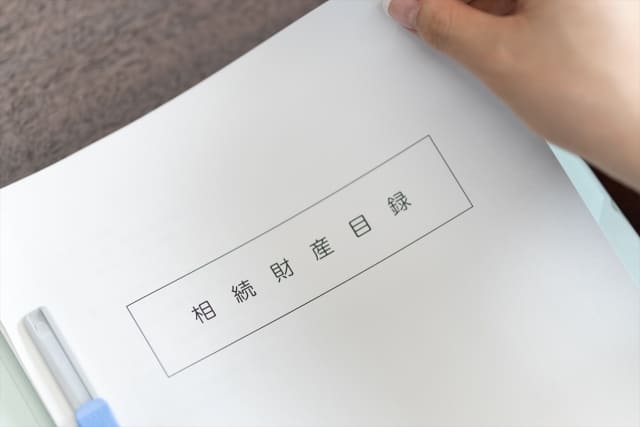※本ページはプロモーションが含まれています。
「亡くなった父がどこに口座を持っていたか分からない」
「実家以外に土地を持っている可能性があるが、どう調べればいい?」
「知らない借金が出てきたらどうしよう……」
相続が発生した際、まず遺族が直面するのが「財産調査」という壁です。
相続財産が確定しなければ、遺産分割協議を進めることも、相続税の申告が必要か判断することもできません。
さらに、「相続放棄」を選択できる期限は死後3ヶ月以内という短い期間であり、迅速かつ正確な調査が不可欠です。
特に2024年からは不動産の相続登記が義務化され、財産の把握漏れが後に過料(ペナルティ)に繋がるリスクも高まっています。
また、近年のデジタル化により「通帳のないネット銀行」や「暗号資産」など、遺族が気づきにくい資産も急増しています。
本記事では、中野区の行政書士が、最新の法令と実務データに基づき、不動産・金融資産から負債まで、漏れのない財産調査の手順を解説します。
なぜ財産調査が重要なのか?
3つの法的リスク
財産調査を「とりあえず分かっている分だけでいい」と済ませてしまうのは非常に危険です。
そこには3つの大きな法的・経済的リスクが潜んでいます。
1. 相続放棄の期限(3ヶ月)を逃すリスク
相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
もし多額の借金があることに気づかず3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として借金をすべて背負わなければなりません。
2. 遺産分割協議「やり直し」のリスク
相続人全員で合意して判を押した「遺産分割協議書」も、後から新たな財産が見つかると、協議自体が無効になったり、再度の話し合いが必要になったりします。
これは親族間のトラブルに発展する最大の原因です。
3. 相続税の「申告漏れ」とペナルティ
国税庁のデータによると、相続税の税務調査で最も多い指摘事項は「現金・預貯金」の申告漏れです。
意図的でなくても、後から財産が見つかれば「過少申告加算税」や「延滞税」が課されることになります。
≪不動産編≫
漏れのない土地・建物調査の手順
不動産は相続財産の中で最も高額になりやすく、かつ「把握しにくい」資産でもあります。
特に地方の山林や、先代の名義のまま放置された土地などは注意が必要です。
1. 郵便物を確認する
(固定資産税の納税通知書)
毎年4月〜6月頃に役所から届く「固定資産税の納税通知書」が最大のヒントになります。
ここにはその自治体内で所有している土地・建物が一覧(課税明細)として記載されています。
2. 「名寄帳(なよせちょう)」を取得する
納税通知書には、非課税の土地(私道など)が載っていないことがあります。
そのため、役所の税務課で「名寄帳」を請求してください。
その自治体内に亡くなった方が所有するすべての不動産が網羅されます。
3. 「相続登記義務化」に伴う登記情報確認
2024年4月から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をすることが義務化されました。
法務局で「登記事項証明書」を取得し、現在の名義人が誰になっているかを確認します。
≪預貯金編≫
通帳がない口座をどう見つけるか?
近年、通帳を発行しない「Web通帳」やネット銀行の普及により、預貯金の調査は難易度が上がっています。
1. 自宅内の徹底捜索
まずは古典的ですが、以下のものを探します。
- 銀行からの封筒、ティッシュ、カレンダーなどのノベルティ
- スマートフォンのアプリ(ネット銀行のアイコンがないか)
- メール履歴(「口座開設完了」「残高のお知らせ」などのキーワード検索)
2. 全金融機関への「残高証明書」請求
心当たりのある銀行に対し、被相続人の死亡日時点の「残高証明書」と、過去数年分の「取引推移明細書」を請求します。
明細を見ることで、他の銀行への振込や、保険料の引き落とし履歴から、別の隠れた資産や負債が見つかることがよくあります。
3. 「名義預金」の確認
亡くなった方の資金で、子供や孫の名義で作った口座(名義預金)は、税務上は「亡くなった方の財産」とみなされます。
これを知らずに除外すると税務調査で指摘されるため、家族名義の口座の出所も確認が必要です。
≪証券・保険編≫
株や投資信託、生命保険の調査
1. 証券会社への照会
証券会社からの郵送物(取引報告書)がないか確認します。
もしどこの証券会社か不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、口座を持っている証券会社を特定できます。
2. 生命保険契約照会制度の活用
2021年から、一般社団法人生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を開始しました。
利用料(3,000円)はかかりますが、亡くなった方がどこの生命保険会社と契約していたかを一括で照会できる画期的な制度です。
≪負債編≫
3つの信用情報機関で調べる
「借金はないはず」と思い込むのが一番危険です。
連帯保証人になっていたケースなども想定し、以下の機関に情報開示請求を行います。
- JICC(日本信用情報機構)
主に消費者金融や信販会社 - CIC(シー・アイ・シー)
主にクレジットカード会社や割賦販売 - 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行や信用金庫、信用保証協会
これら3か所に照会をかければ、亡くなった方の生存時の借り入れ状況がほぼ完全に把握できます。
≪デジタル遺産≫
スマホやPCに眠る「見えない資産」
2025年現在、最もトラブルが増えているのがデジタル遺産です。
- ネット証券・暗号資産(仮想通貨)
IDやパスワードが分からないとログインすらできず、放置されるリスクがあります。 - サブスクリプション(月額課金)
動画配信やクラウドサービスなど、死亡後もクレジットカードから引き落とされ続けるケースがあります。

調査結果をまとめる「遺産目録」の作成
すべての調査が終わったら、必ず「遺産目録」を作成します。
これは、遺産分割協議の基礎資料となるだけでなく、相続税申告の際の重要な証拠資料となります。
遺産目録に記載すべき項目
- 不動産
所在、地番、面積、評価額 - 預貯金
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高 - 有価証券
銘柄、数量、評価額 - 負債
借入先、残高 - その他
貴金属、書画骨董、自動車など
行政書士に財産調査を依頼するメリット
財産調査は、自分で行うことも可能ですが、膨大な時間と精神的な負担がかかります。
1. 職権による迅速な書類取得
行政書士は、職務上請求により戸籍謄本を迅速に収集し、それを持って各金融機関や役所への調査をスムーズに行えます。
2. 「見落とし」を防ぐ専門眼
取引明細から「この振込先は生命保険ではないか?」「この固定資産税の金額からすると、他にも土地があるはずだ」といったプロの推察により、隠れた財産を掘り起こします。
3. 公平・中立な報告
相続人の一人が調査を行うと、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑われることがあります。
第三者である専門家が調査・報告することで、親族間の信頼関係が保たれます。
よくある質問(FAQ)
正確な調査が「争族」を防ぐ唯一の手段
相続財産の調査は、相続手続きという長い道のりの「地図」を作る作業です。
地図が間違っていれば、どれだけ努力しても正しいゴール(円満な相続)には辿り着けません。
2024年の相続登記義務化や、デジタル資産の多様化により、調査の重要性はかつてないほど高まっています。
- 財産調査は「相続放棄」ができる3ヶ月以内を目標に完了させる
- 不動産は「納税通知書」だけでなく「名寄帳」で私道共有持分まで確認する
- 2024年4月より、全不動産の相続登記が法律で義務化された
- 銀行口座は取引明細を遡り、保険や他口座への「資金の動き」を追う
- 生命保険や証券口座は、業界全体の一括照会制度を賢く利用する
- 負債の有無は、3つの信用情報機関に照会をかけるのが最も確実である
- ネット銀行やサブスクなど、スマホの中に眠る「デジタル遺産」を見落とさない
中野区のかとう行政書士事務所では、戸籍収集から不動産・金融資産の徹底調査、そして遺産目録の作成まで、相続の「入り口」を完璧に整えるサポートを行っております。
「自分たちで調べたが、まだ何かある気がして不安だ」「仕事が忙しくて銀行を回る時間がない」という方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
皆様の大切な財産を漏れなく整理させていただきます。
お問い合わせは、お電話または24時間対応のフォームより受け付けております。
正しい現状把握こそが、家族の絆を守り、スムーズな相続を実現するための最大の鍵です。
私たちが、専門家としての確かな知見で、皆様の新たな一歩を全力でバックアップいたします。