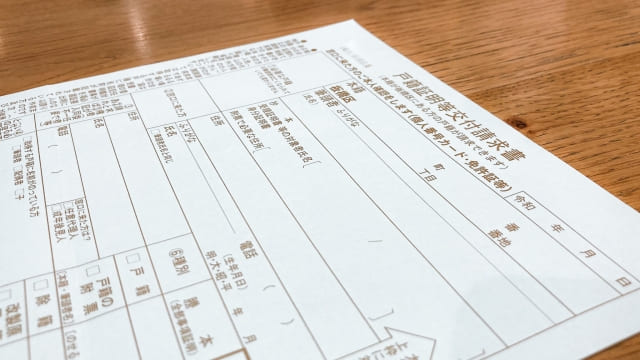※本ページはプロモーションが含まれています。
「銀行や法務局へ行くたびに、分厚い戸籍の束を持ち歩くのが大変……」
「戸籍謄本の原本を何セットも用意するのはお金がかかりすぎる」
相続手続きを始めたばかりの方が直面する共通の悩みが、「戸籍謄本の山」の扱いです。
通常、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、一式揃えると10枚以上の束になることも珍しくありません。
これを各金融機関や法務局に提出し、確認を待つ作業は非常に時間がかかります。
この問題を一気に解決するのが、法務局が発行する「法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)」です。
これ一枚あれば、煩雑な戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
本記事では、中野区で相続実務に特化する行政書士が、最新の制度運用に基づき、法定相続情報一覧図のメリット、作成手順、そしてなぜ今の相続において「必須」と言われるのかを解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月から始まった、比較的新しい制度です。
制度の概要
相続人が法務局に対し、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式と、家系図のような形式でまとめた「法定相続情報一覧図」を提出します。
法務局の登記官がその内容を確認し、間違いがないと認めれば、法務局の認証印が入った「公的な証明書」を無料で発行してくれます。
2024年以降、なぜ注目されているのか
最大の理由は、2024年4月1日からスタートした「相続登記の義務化」です。
不動産の名義変更が義務付けられたことで、法務局への申請件数が急増しています。
この制度を利用すれば、不動産登記だけでなく、銀行の手続きや相続税の申告もスムーズに進むため、利用者が急速に増えているのです。 (参照:法務省「法定相続情報証明制度について」)
法定相続情報一覧図を利用する
5つの劇的なメリット
この制度を利用することで、相続手続きの負担は驚くほど軽減されます。
1. 戸籍謄本の原本が「1セット」で済む
通常、銀行A、銀行B、法務局、税務署と、複数の窓口で同時に手続きを進めるには、戸籍謄本の束をその数だけ用意しなければなりません。
戸籍は1通450円〜750円するため、複数セット用意すると万単位の出費になります。
この制度を使えば、戸籍は1セットあればOKです。
法務局から発行される証明書は何枚でも無料で発行されるため、大幅なコストダウンになります。
2. 手続きの待ち時間を大幅に短縮
銀行の窓口で戸籍の束を出すと、担当者が1枚ずつ読み解き、コピーを取るのに30分〜1時間以上待たされることがよくあります。
法定相続情報一覧図を提出すれば、銀行側は「法務局が確認済みの1枚の書類」を確認するだけで済むため、確認作業が劇的に早まります。
3. 有効期限がない(多くの機関で共通)
戸籍謄本そのものは「発行から3ヶ月以内」などの期限を求められることが多いですが、法定相続情報一覧図は、その性質上、内容に変化がない限り、長期間有効として受け付けてくれる機関が多いのが特徴です。
4. 5年間は無料で再発行が可能
一度法務局に登録すれば、一覧図のデータは法務局に5年間保存されます。
後から「新しい銀行口座が見つかった」という場合でも、委任状なしで(または簡単な手続きで)再発行を受けることができます。
5. 相続税申告や年金手続きにも対応
現在、ほとんどの主要な金融機関、証券会社、法務局、税務署、年金事務所でこの証明書が戸籍謄本の代わりとして認められています。
≪実務データ≫
制度の利用状況と行政書士の役割
法務省の公表データによると、法定相続情報証明制度の申出件数は年々右肩上がりで推移しています。
しかし、その多くは行政書士や司法書士などの専門家による代理申出です。
なぜなら、この制度を利用するためには、結局のところ「一度は全ての戸籍を完璧に集め、正確な図面(一覧図)を作成しなければならない」からです。
専門家が作成する「一覧図」の正確性
一覧図には、氏名の漢字一文字のミスも許されません。
また、代襲相続が発生している場合や、数次相続(相続が重なっている場合)など、図面作成が極めて複雑になるケースがあります。
行政書士は、これらの複雑な家系関係を法的に正しく整理し、法務局に受理される書類を迅速に作成します。
法定相続情報一覧図を作成する
具体的な手順
ご自身で作成を検討されている方のために、実務上のフローを解説します。
≪ステップ1≫
戸籍謄本等の収集
これが最も高いハードルです。
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍、除籍、改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類
これらをすべて揃えます。

≪ステップ2≫
法定相続情報一覧図の起案
法務局が指定する様式(A4白紙)に、被相続人と相続人の関係を図形式、または列挙形式で記載します。
パソコン(WordやExcel)で作成するのが一般的ですが、手書きでも可能です。
※住所を記載しておくと、その後の不動産登記や銀行手続きがよりスムーズになるため、実務上は「住所付き」の一覧図を作成するのが定石です。
≪ステップ3≫
申出書の作成と提出
管轄の法務局(被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人の不動産の所在地)へ、申出書と添付書類を提出します。郵送での申請も可能です。
≪ステップ4≫
証明書の交付
不備がなければ、数日から1週間程度で認証印の押された証明書が発行されます。
知っておくべき制度の「限界」と注意点
非常に便利な制度ですが、万能ではない点にも注意が必要です。
1. 「遺産を誰が継ぐか」は書いていない
この証明書は、あくまで「誰が法的相続人か」を証明するだけのものです。
「長男がすべての不動産を継ぐ」といった遺産分割協議の内容までは反映されません。
そのため、銀行手続きなどでは、この証明書に加えて「遺産分割協議書」と「印鑑証明書」がセットで必要になります。
2. 相続放棄した人は「相続人」として載る
相続放棄をした人がいても、戸籍上の関係は変わらないため、一覧図にはそのまま記載されます。
別途、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を併せて提出する必要があります。
3. 日本国籍がない場合は利用できない
被相続人や相続人が日本国籍を有しない(戸籍がない)場合は、この制度を利用することができません。
4. 申出ができる人が限られている
申出ができるのは、相続人のほか、その代理人(親族や行政書士等の資格者)に限られます。
相続登記義務化時代の「賢い」活用術
2024年4月からの相続登記義務化により、不動産をお持ちの方は必ず法務局と関わることになります。
この際、単に登記を申請するだけでなく、「ついでに法定相続情報一覧図も作っておく」のが最も効率的な相続手続きの進め方です。
口座解約のみのケースでも有効
最近では、スマホ決済やネット銀行など、少額の口座が複数見つかるケースが増えています。
それぞれの銀行に戸籍の束を送るのは非効率です。
法定相続情報一覧図を数枚取っておけば、複数のネット銀行への郵送手続きを同時並行で進めることができ、完了までの期間を数ヶ月単位で短縮できます。
法定相続情報一覧図作成を、
行政書士に依頼するメリット
ミスのない図面作成
古い戸籍の判読ミスによる「作成し直し」は、時間の大幅なロスに繋がります。
プロの視点で、一発で受理される図面を作成します。
全体のコンサルティング
一覧図を作る過程で、相続人の状況や財産の全容が明確になります。
その後の遺産分割協議書作成や、他士業(司法書士・税理士)へのスムーズなバトンタッチまでを見据えたアドバイスが可能です。
心理的負担の軽減
親族を亡くした直後に、慣れない法務局の窓口とやり取りするのは精神的な負担が大きいものです。
専門家が間に入ることで、事務的な苦労から解放されます。
効率的な相続手続きの「鍵」は、
法務局にある
法定相続情報一覧図は、現代の複雑な相続手続きをスマートに変える「鍵」のような存在です。
特に相続登記が義務化された今、この制度を利用しない手はありません。
- 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の束を1枚の証明書にまとめる法務局の制度である
- 証明書の発行手数料は「無料」で、何枚でも発行可能(戸籍代の節約になる)
- 2024年4月からの相続登記義務化により、利用の重要性がさらに高まっている
- 銀行、証券会社、税務署など、ほとんどの相続手続き先で共通して利用できる
- 作成には「出生から死亡までの戸籍収集」と「正確な家系図の作成」が必須である
- 行政書士に依頼すれば、戸籍収集から図面作成、法務局への申出まで丸投げできる
相続手続きは、最初の「書類集め」で挫折してしまう方が最も多いのが実情です。
法定相続情報一覧図を早めに作成しておくことで、その後の手続きすべてが驚くほどスムーズになります。
中野区のかとう行政書士事務所では、最新の法改正に基づき、お客様の状況に合わせた最適な手続き順序をご提案します。
「戸籍集めが難航している」「銀行手続きを早く終わらせたい」という方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
お問い合わせフォームよりいつでも受け付けております。
面倒な書類仕事は私たち専門家に任せ、皆様は大切な方との思い出を振り返り、ご家族とのこれからの時間を大切になさってください。
私たちが、正確・迅速にそのお手伝いをさせていただきます。