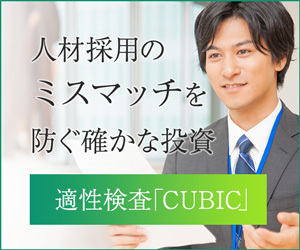※本ページはプロモーションが含まれています。
東京都中野区の行政書士で、中小企業向けの採用支援を行っております、かとう行政書士事務所です。
「せっかく面接に来てくれても、入社後に『こんなはずではなかった』というミスマッチが発生してしまう…」
「面接では良い人だと思ったのに、現場で全く活躍できない」
これは、採用面接における「質問の質の低さ」が原因であるケースが非常に多いです。
定型的な質問ばかりでは、応募者は準備した「模範解答」しか話してくれず、その人の真の思考や行動特性を見抜くことはできません。
面接官の役割は、単に質問を投げかけることではなく、応募者が最も自分らしく、本音で語れる「安全な場」を設計することです。
本記事では、中小企業の採用担当者や経営者様向けに、採用のミスマッチを最小化し、「入社後に活躍する人材」を見抜くための「面接官の質問力」を徹底的に強化する方法を解説します。
特に、行動特性(コンピテンシー)を引き出すための構造化面接の具体的なテクニックと面接における法令遵守について深く掘り下げます。
なぜ「質問の設計力」が
採用の成否を分けるのか?
質の高い質問は、応募者の過去の具体的な行動(=未来の行動予測)と価値観を引き出し、採用の精度を飛躍的に高めます。
「模範解答」の壁を打ち破る質問構造
従来の面接でよくある「志望動機」「長所・短所」といった質問は、書籍やインターネットで対策が可能です。
面接官が知りたいのは、「何をしたか」ではなく「なぜそうしたか」「その結果どう考えたか」という応募者の思考プロセスと判断軸です。
面接を「対話」に変え、応募意欲を高める
質問力を高めることは、応募者体験の向上にも直結します。
一方的な質問攻めではなく、興味と敬意を持った深掘りは、「この会社は自分をちゃんと見てくれている」という印象を与え、内定承諾率を高める要因となります。
客観的な評価基準を担保する(構造化面接)
面接官の「直感」や「相性」に頼ってしまうのは、採用ミスマッチの最大の原因です。
あらかじめ評価したい「コンピテンシー(行動特性)」に基づいた質問と評価基準を設計する「構造化面接」は、面接の客観性を高め、採用の質を安定させます。
行動特性を見抜く質問テクニック
活躍する人材の過去の行動を引き出すための具体的な質問方法として、「STAR/CAR」フレームワークを応用した深掘り手法が有効です。
| フレームワーク | 意味 | 質問の意図 |
| Situation(状況) | どんな状況・課題だったか | 課題の背景と難易度を把握する |
|---|---|---|
| Task(課題/目標) | どんな目標やミッションだったか | 応募者の目的意識を測る |
| Action(行動) | あなた自身が具体的にどう行動したか | 応募者の主体性・行動力を深掘りする |
| Result(結果) | どのような結果になったか | 成果と、結果に対する自己評価を把握する |
具体的な「深掘り質問」の例
- 結果を聞いた後
「その結果を得るまでに、あなたが最もこだわった行動は何ですか?」 - 成功体験を聞いた
「もし同じ状況が再来したら、今度は何を改善しますか?」 - 抽象的な回答に対し
「〇〇さんが、具体的に最初に行った行動を教えてください」 - チームでの行動を聞いた後
「チームメンバーの中で、あなた自身の役割と、あなたにしかできなかったことは何ですか?」
これらの質問は、「その人自身の考えと行動の連鎖」を明らかにし、単なる「過去の事実」ではなく、「未来の再現性」を予測するための根拠となります。
面接官に求められる
「傾聴力」「場のコントロール力」
質問設計が優れていても、面接官の「聞き方」が応募者の本音を閉ざしてしまうことがあります。
積極的傾聴の技術
応募者が話しやすい雰囲気を作るために、以下の「傾聴の姿勢」が不可欠です。
- 復唱と要約
「つまり、〇〇という目標に対し、あなたは△△という行動を取られたということですね?」
と相手の言葉を繰り返すことで、理解を示し、話の誤解を防ぎます。 - 沈黙を恐れない
応募者が考えている時間(沈黙)を面接官が埋めてしまうと、深い思考を妨げます。
数秒間の沈黙を許容することで、応募者自身の言葉を引き出します。
中小企業だからこそ伝えたい「自社の魅力」
面接官は、「採用する側」であると同時に「自社を売り込む営業マン」でもあります。
面接の終盤で、「あなたが当社の仕事で活かせそうなスキル」と「当社があなたに期待する役割」を具体的に伝えることで、特別感と入社後のイメージを明確化し、応募意欲を高めます。
面接における法令遵守とNG質問の回避
採用面接は、企業のコンプライアンス意識が試される場です。
不適切な質問は、企業の評価を下げるだけでなく、法令違反のリスクも伴います。
職業差別やプライバシー侵害
厚生労働省が定める指針に基づき、人権を侵害する可能性がある質問は絶対に行ってはなりません。
| NG質問の例 | 懸念されるリスク |
| 家族構成、出生地、本籍地 | 就職差別につながるおそれ |
|---|---|
| 結婚・出産の予定、恋人の有無 | プライバシー侵害、男女雇用機会均等法に抵触するおそれ |
| 思想・信条・支持政党・信仰する宗教 | 思想の自由の侵害 |
これらの質問は、仕事に直接関係がなく、応募者の属性で採否を決める差別的な採用と見なされるリスクがあります。
記録・評価の徹底による公正性の担保
面接の質と公正性を高めるため、面接官は「質問と応募者の回答」、そして「評価理由」を詳細に記録する義務があります。
この記録は、採用プロセスの透明性を高め、後に不当な採用だと指摘された際の法的証拠にもなり得ます。
この記事のまとめ
中小企業の採用の成否は、面接官が質問力を通じて応募者の本音と行動特性をどこまで引き出せるかにかかっています。
- 質問の設計
コンピテンシーに基づき、応募者の「行動」と「思考プロセス」を掘り下げる質問を事前に準備する。 - 対話の技術
傾聴と復唱を通じて信頼関係を築き、応募者に気持ちよく本音を話してもらう。 - 法令遵守
NG質問を厳禁し、公正でプロフェッショナルな面接を実施することで、企業の信頼性を高める。
面接官が「プロの聴き手」となり、面接を「単なる試験」から「お互いの未来を確認し合う対話の場」へと変えることこそ、優秀な人材を獲得する最短ルートです。
▼ご相談は下記よりお気軽に▼
本記事でご紹介した商品やサービスは、筆者の個人的な感想および調査に基づいております。
読後の感じ方や効果には個人差がありますので、あらかじめご了承ください。
料金やサービス内容は記事作成当時の情報ですので、最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
本記事には一部アフィリエイトリンクが含まれており、読者の皆さまがリンク先の商品やサービスをご購入またはご利用された場合、筆者に報酬が発生することがあります。
紹介する内容や評価には影響を与えておらず、公平な視点でご紹介することを心がけています。
ここでご紹介した商品やサービスが皆さまのお役に少しでも立ちますように──。