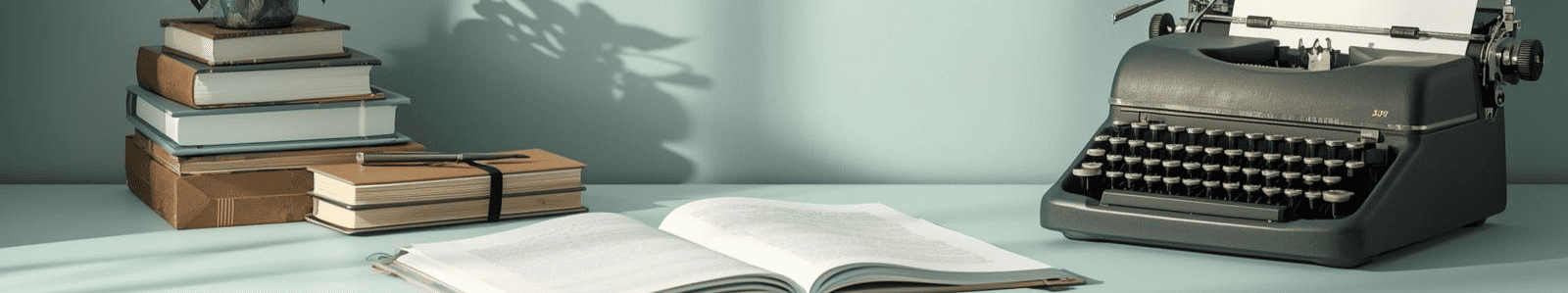疑問・不安は、相談前にここで解消。 よくいただくご質問をまとめました。
行政書士の業務は多岐にわたるため、
「自分の悩みは対応してもらえるのか?」
「費用はいくらかかるのか?」
など、多くの疑問をお持ちかと思います。
こちらでは、これまでに皆様から寄せられた主なご質問をカテゴリー別に掲載しております。
ここに載っていない疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてお尋ねください。

相談・依頼全般について
- 行政書士には、具体的に何を依頼できるのですか?
-
行政書士は「官公庁に提出する書類」や「権利義務・事実証明に関する書類」の作成代理を行う国家資格者です。
具体的には、建設業や飲食店の営業許可申請、外国人のビザ申請、会社設立の手続き、遺言書や遺産分割協議書の作成、車庫証明の取得など、その範囲は数千種類に及びます。
「役所への手続き」や「法的な書類作成」でお困りの際は、まず私たちにご相談ください。
- 自分の悩みが行政書士の業務なのか、弁護士や司法書士の業務なのか分かりません。
-
ご安心ください。
お客様がそれを判断する必要はありません。
まずは当事務所にご相談いただければ、当事務所で対応可能か判断いたします。
もし裁判や登記、税務申告など、他の専門家の独占業務である場合は、信頼できる弁護士、司法書士、税理士などを無料でご紹介いたします。
当事務所は、お客様のお困りごとを適切な解決へ導く「最初の窓口」としての役割も担っています。
- まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでもいいですか?
-
はい、もちろんです。
初回相談(60分程度)は無料で行っております。
お話をお伺いし、手続きの流れやメリット・デメリットをご説明します。
その上で、ご自身で手続きされるか、当事務所に依頼されるかをご判断ください。
無理な勧誘は一切いたしません。
- 個人情報は安全に管理されますか?
-
はい、もちろんです。
個人情報は厳重に管理し、プライバシーポリシーに基づいて取り扱います。
- こんな初歩的な質問でも相談していいですか?
-
もちろんです。
「こんなこと聞いていいのかな?」という内容ほど、多くの方が同じ悩みを抱えています。
お気軽にご相談ください。

費用・契約について
- 相談料はいくらですか?
-
初回の相談は無料です。
2回目以降のご相談は30分5,500円(税込)を頂戴しますが、そのまま業務をご依頼いただいた場合は、着手金に充当しますので実質無料となります。
- 料金表に載っていない業務の費用を知りたいです。
-
業務内容が多岐にわたるため、ホームページには代表的な業務の料金のみ掲載しております。
個別のお悩みについては、内容や難易度をお伺いした上で、必ず着手前に詳細なお見積書を作成・提示いたします。
- 追加料金が発生することはありますか?
-
原則として、当初のお見積り以外の追加報酬はいただきません。
ただし、業務の途中で「新たな手続きが必要になった」「お客様の事情が変わり申請内容が大幅に変更になった」といった場合は、事前にご説明し、改めてお見積りをご提示した上で進めさせていただきます。
勝手に追加請求することはございません。
- 支払いのタイミングと方法を教えてください。
-
基本的には、業務着手時に「着手金(報酬+実費概算)」を、業務完了時に「残金」をお支払いいただきます。
お支払い方法は、銀行振込のほか、現金払いに対応しております。
詳細はお問い合わせ時にご案内します。

個人のお客様
(相続・ビザ・車など)
- 【相続】相続人が誰なのか分かりません。戸籍の収集だけ頼めますか?
-
はい、可能です。
相続手続きの中で最も大変なのが、出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集です。
当事務所では、相続人調査(戸籍収集)のみのスポット依頼も承っております。
収集した戸籍を整理し、「相続関係説明図」を作成してお渡しします。
- 【遺言】遺言書は自分で書くのと公正証書にするの、どちらが良いですか?
-
確実性を求めるなら公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。
当事務所では、公証役場との打ち合わせや証人の手配を含め、公正証書遺言の作成をフルサポートいたします。
- 【ビザ】外国人の友人を呼びたいのですが、絶対に許可が下りますか?
-
残念ながら、入管手続きにおいて「100%の許可」を保証することは誰にもできません。
しかし、行政書士に依頼することで、法令や審査基準に基づいた適切な書類を作成し、許可の可能性を最大限に高めることは可能です。
万が一不許可になった場合の再申請や、理由の確認などもサポートします。
- 【車】車庫証明は、依頼してから何日くらいでできますか?
-
警察署の標準処理期間は、申請してから「中2日〜3日(土日祝除く)」です。
当事務所にご依頼いただければ、書類が揃い次第、即日〜翌日には管轄警察署へ申請いたします。
お急ぎの場合は特急対応もご相談ください。

法人・事業主のお客様
(建設業・会社設立など)
- 【建設業】「500万円以下の工事」しかしないのですが、許可は必要ですか?
-
原則として不要ですが、許可を取得するメリットはあります。
近年はコンプライアンスの観点から、元請業者や発注者が「金額に関わらず許可業者であること」を発注条件にするケースが増えています。
また、金融機関からの融資において信用力が増すメリットもあります。
将来的な事業拡大を見据えて取得されることをおすすめします。
- 【会社設立】自分で設立するのと、行政書士に頼むので何が違いますか?
-
最大の違いは「手間」と「費用対効果」です。
会社設立における最初の壁が定款作成です。
行政書士に依頼することで、面倒な手続きを丸投げできるとともに、抜けや漏れの無いプロが作成した間違いのない定款の作成が可能となります。
- 【補助金】補助金の申請代行はお願いできますか?
-
はい、対応可能です。
小規模事業者持続化補助金や事業再構築補助金など、採択されるためには「説得力のある事業計画書」が不可欠です。
当事務所では、お客様の強みを引き出し、審査員に伝わる計画書の作成を支援します。
ここに載っていない手続きでもご相談ください!!
「行政書士ができること」は非常に幅広いため、すべてを掲載することはできません。
「こんな書類を作りたい」「手続きで困っている」ということがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
もし当事務所で対応できない場合でも、適切な相談先をご案内いたします。