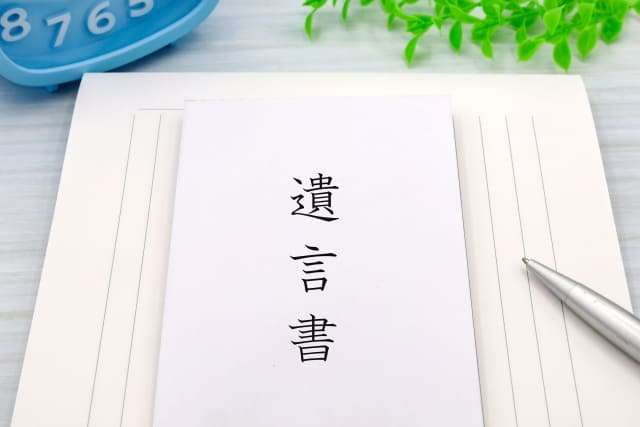※本ページはプロモーションが含まれています。
「遺言書」はどれを選べばいい?失敗しないための選択基準
「遺言書を書こうと思ったけれど、種類がいくつかあってどれを選べばいいかわからない」
「手書きで簡単に済ませたいけれど、無効にならないか心配……」
遺言書は、あなたの財産と想いを大切な人に託すための、人生最後の、そして最も重要な法的文書です。
しかし、遺言書には民法で定められた厳格なルールがあり、その形式は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が存在します。
それぞれの遺言には明確なメリット・デメリットがあり、あなたの財産状況、家族関係、そして予算によって「正解」は異なります。
さらに、近年の民法改正により、自筆証書遺言のルールが緩和され、法務局での保管制度が始まるなど、選択肢はより広がり、かつ複雑になっています。
この記事では、遺言・相続業務を専門とする行政書士が、3つの遺言形式の特徴と違い、最新の法改正による変更点、そしてあなたに最適な遺言形式を選ぶための判断基準を解説します。
民法が定める遺言の「3つの種類」
基本構造
民法で定められた「普通方式」の遺言は、以下の3種類です。
それぞれ作成方法、保管方法、開封時の手続き(検認の要否)が異なります。
| 遺言の種類 | 作成者 | 保管場所 | 検認(家庭裁判所) | 特徴 |
| 1. 自筆証書遺言 | 本人(自筆) | 自宅または法務局 | 必要(法務局保管は不要) | 手軽だが不備・紛失リスクあり |
|---|---|---|---|---|
| 2. 公正証書遺言 | 公証人 | 公証役場 | 不要 | 最も確実で安全。費用がかかる |
| 3. 秘密証書遺言 | 本人(署名は自筆) | 自宅 | 必要 | 内容を秘密にできるが利用は稀 |
≪種類1≫
自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)
最も手軽で、費用をかけずに作成できるのが自筆証書遺言です。
しかし、形式不備による無効トラブルが最も多いのもこの形式です。
作成のルールと法改正による緩和
(財産目録のPC作成)
基本ルール
- 全文を自筆で書くこと。
- 日付を正確に書くこと(「吉日」などは不可)。
- 署名・押印すること。
「自筆証書遺言書保管制度」活用メリット
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度がスタートしました。
これにより、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・改ざん・検認の手間」が解消されました。
- メリット
- 検認不要
死後、すぐに相続手続きに使用できます。 - 形式チェック
保管申請時に法務局職員が外形的なチェックを行うため、形式不備のリスクが減ります。
(内容の有効性は保証されません) - 紛失・改ざん防止
公的機関で厳重に保管されます。
- 検認不要
- 費用
手数料は1通3,900円と、公正証書遺言に比べて非常に安価です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
- メリット
費用が安い、誰にも知られずに作成できる、いつでも書き直せる。 - デメリット
形式不備で無効になりやすい、認知症などで書いた場合「本人の意思か」が争われやすい、発見されないリスクがある。(自宅保管の場合)

≪種類2≫
公正証書遺言
(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で、法律のプロである「公証人」に作成してもらう遺言です。
実務上、最も推奨される確実な方式です。
作成の流れと証人の役割
- 事前の打ち合わせ
公証人と遺言内容について打ち合わせを行い、文案を作成します。
(行政書士等が代行可能) - 証人2名の立会い
作成当日、利害関係のない証人2名の前で、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記します。 - 署名・押印
内容を確認後、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成です。
公正証書遺言の圧倒的なメリット
- 無効リスクがほぼゼロ
公証人が作成するため、形式不備や内容の不明確さによる無効が防げます。
また、公証人が遺言能力(判断能力)を確認するため、後で「認知症だったから無効だ」と争われるリスクも低減できます。 - 検認不要
死後、家庭裁判所の検認手続きなしで、即座に銀行解約や不動産登記に使用できます。 - 原本の保管
原本は公証役場に半永久的に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
気になる費用(公証人手数料)の目安
公正証書遺言は、遺産額に応じた手数料がかかります。
| 目的の価額(遺産額) | 手数料 |
| 1,000万円まで | 11,000円 |
|---|---|
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
≪種類3≫
秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言の内容を誰にも(公証人にさえ)知られずに、遺言書の存在だけを公証して保管する方式です。
特徴と利用の少なさ
遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人と証人2名の前で「これが私の遺言書です」と申述し、署名押印します。
- メリット
内容を完全に秘密にできる。パソコン作成や代筆も可能。
(署名は自筆) - デメリット
公証人は内容を確認しないため、内容の不備で無効になるリスクが高い。
検認が必要。
保管は自己責任。
あなたに最適な遺言書はどれ?
選び方のフローチャート
状況別に、どの遺言形式を選ぶべきかの判断基準を整理しました。
≪パターンA≫
公正証書遺言を選ぶべき人
- 「争族」のリスクがある人
相続人同士の仲が悪い、前妻の子がいる、内縁の妻がいる場合など。 - 病気や高齢で自筆が困難な人
手が震えて文字が書けない場合でも、公正証書なら作成可能です。 - 確実に遺言を執行してほしい人
無効リスクを排除し、家族に負担(検認手続き)をかけたくない場合。 - 財産が複雑・多額な人。
≪パターンB≫
自筆証書遺言(法務局保管)を選ぶべき人
- 費用を抑えたい人
数万円の手数料をかけたくない場合。 - 内容を誰にも知られたくない人
ただし、死後に発見されるための工夫(保管制度の通知機能など)が必要です。 - 若くて健康だが、とりあえず書いておきたい人
将来書き直す前提で、まずは自分の想いを形にしておきたい場合。
遺言書作成で失敗しない!
行政書士活用術
どの種類の遺言書を選ぶにしても、最も重要なのは「内容の法的妥当性」です。
「遺留分」への配慮と「付言事項」の活用
特定の相続人に全財産を譲るような遺言は、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害し、死後のトラブル(遺留分侵害額請求)の原因になります。
行政書士は、遺留分を考慮した配分案や、争いを防ぐためのメッセージ(付言事項)の書き方をアドバイスします。
行政書士によるサポート範囲
- 相続人調査・財産調査
戸籍謄本や不動産登記事項証明書を収集し、正確な財産目録を作成します。 - 文案作成
法的効力のある正確な言葉で遺言書案を作成します。 - 公証役場との調整
公正証書遺言の場合、公証人との事前協議をすべて代行します。 - 証人の引受け
公正証書遺言作成時の証人2名として立ち会います。 - 遺言執行者への就任
死後、遺言の内容を実現する「遺言執行者」として指定しておくことで、不動産登記や預金解約をスムーズに行います。
最適な遺言形式を選び
想いを確実に届けよ
遺言書は、残された家族への「最後のラブレター」であり、家族を争いから守るための「最強の法的ツール」です。
その効力を最大限に発揮するためには、自分に合った形式を選び、法的な不備がないように作成することが不可欠です。
- 遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があり、それぞれ法的効力の確実性や費用が異なります。
- 自筆証書遺言は、法改正により財産目録のパソコン作成が可能になり、法務局での保管制度(検認不要)を利用することで安全性が高まりました。
- 公正証書遺言は、公証人が作成するため無効リスクがほぼなく、検認も不要で最も確実な方法ですが、費用と証人が必要です。
- 相続トラブルが予想される場合や、確実に遺言を執行したい場合は、コストをかけてでも公正証書遺言を選ぶべきです。
- 行政書士に依頼することで、戸籍・財産調査、文案作成、公証役場との調整、証人の手配をワンストップで任せることができ、法的にも安心な遺言書を作成できます。
「自分にはまだ早い」「書き方がわからない」と先延ばしにせず、まずは専門家に相談して、あなたの状況に最適な遺言書の形を見つけることから始めましょう。
それが、家族の未来を守る第一歩となります。