※本ページはプロモーションが含まれています。
「子供がいないから、全て妻(夫)が継ぐ」という思い込みの恐ろしさ
「私たちには子供がいないから、どちらかが死んだら全ての財産はもう一方の配偶者が受け取るはずだ」
「夫婦二人で築き上げた財産なのだから、他人が口を出す余地はない」
もしあなたがそのように考えているなら、2025年現在の日本の相続法において、それは極めて危険な誤解です。
行政書士として多くの相談を受ける中で、最も「想定外のトラブル」に発展し、残された配偶者が涙を流すのが、このおふたりさま(子なし夫婦)のケースです。
結論から申し上げます。
遺言書がない場合、配偶者だけでなく、あなたの兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が法定相続人として現れます。
長年交流がなかった義理の兄弟と、自宅や預貯金を分け合わなければならないのです。
2024年4月から始まった相続登記の義務化により、不動産の名義変更を放置することも許されなくなりました。
今回は、子供がいない夫婦が直面する過酷な相続の現実と、それを回避して配偶者に100%財産を遺すための「最強の遺言戦略」を解説します。
おふたりさま相続の法的現実
なぜ「義兄弟」が登場するのか
まずは、日本の民法が定める相続の優先順位を正しく理解しましょう。
相続権の第3順位:兄弟姉妹の壁
子供がいない夫婦の場合、相続権は以下のように移動します。
- 第1順位
配偶者と子供(子供がいないので不在) - 第2順位
配偶者と直系尊属(親や祖父母。既に他界していることが多い) - 第3順位
配偶者と兄弟姉妹
法定相続分の割合
(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)
遺言書がない場合、配偶者が全財産を相続できるわけではありません。
法律上の取り分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1となります。
たった4分の1と思われるかもしれませんが、自宅不動産が含まれる場合、この4分の1を現金で支払う(代償分割)ことができず、住み慣れた家を売却せざるを得ないケースもあるのです。
おふたりさまを襲う
「3つの相続リスク」
行政書士の現場で実際に起きている、子なし夫婦特有の悲劇を紹介します。
印鑑を貰わなければ「1円も引出せない」
銀行口座の凍結解除や不動産の登記変更には、相続人全員の署名と実印(遺産分割協議書への押印)が必要です。
普段付き合いのない義理の兄弟や、会ったこともない甥・姪に連絡を取り、実印をお願いしなければなりません。
「自分たちの財産だから」という理屈は通用せず、一人でも拒否すれば、配偶者の生活資金は完全にストップします。
「ハンコ代」という名の過大な要求
「長年、兄さんには世話になった」「うちも生活が苦しいから、法定分はしっかりもらいたい」。
そう主張する親族は少なくありません。
夫婦二人で節約して貯めた老後資金が、相続というタイミングで合法的に他家へ流出していく現実に、多くの配偶者が深い喪失感と怒りを覚えます。
相続登記義務化による時間切れ
2024年4月から、相続を知った日から3年以内に名義変更をしないと10万円以下の過料(罰則)が科されるようになりました。
義兄弟との話し合いが難航し、3年が経過してしまえば、残された配偶者は精神的苦痛だけでなく金銭的罰則まで背負わされることになります。

解決策はこれだけ
おふたりさま専用「全財産遺贈」遺言
この地獄のような状況を一瞬で解決する方法があります。
それが遺言書の作成です。
≪重要ポイント≫
兄弟姉妹には「遺留分」がない
ここが最も重要なポイントです。
子供や親には、遺言書があっても最低限の取り分を主張できる「遺留分」がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1028条)。
つまり、「妻(夫)に全財産を相続させる」という一行の遺言書があるだけで、兄弟姉妹の相続権を完全に、合法的にゼロにできるのです。

遺言書があれば「遺産分割協議」が不要
遺言書があれば、他の相続人の署名や実印、連絡すら一切不要になります。
残された配偶者は、遺言書を銀行や法務局に持っていくだけで、自分一人で手続きを完了させることができます。
これが、おふたりさまにとって遺言書が「最強のラブレター」と呼ばれる所以です。
二次相続まで見据えた「予備的遺言」
おふたりさまの相続対策で、プロの行政書士が必ずアドバイスするのが二次相続(後死者)の問題です。
夫婦で同時に書く「夫婦相互遺言」
夫が先に死んだら妻へ。
妻が先に死んだら夫へ。
このようになるように、夫婦別々に遺言を書くことが基本です。
しかし、2025年の最新実務ではさらに一歩進みます。
「予備的遺贈」の条項を入れる
もし、受取人である配偶者が自分より先に、あるいは同時に亡くなってしまったらどうなるか。
その場合、遺言書は失効し、結局はまた義兄弟同士の争いに戻ってしまいます。
「もし妻(夫)が先に亡くなっている場合は、私の財産を〇〇(姪、友人、あるいは自治体・NPOへの寄付など)に遺す」という予備的遺言を添えることで、財産の最終的な行き先までをコントロールできます。
事実婚・パートナーシップ関係における
「遺言」の死活的重要性
2025年、多様な家族の形が増えていますが、法律上の「籍」が入っていないおふたりさまにとって、遺言書は「命綱」そのものです。
事実婚には「1円の相続権」もない
どれほど長く連れ添っても、法律婚でない限り、パートナーには相続権が一切ありません。
あなたが亡くなった場合、財産はすべてあなたの親族(親や兄弟)に行き、パートナーは住んでいる家から明日出て行かなければならないという事態すら起こり得ます。
「特別縁故者」を待つより遺言書
「特別縁故者」として財産分与を求める道もありますが、裁判所の審判が必要で、確実性は低く、時間もかかります。
公正証書遺言で「パートナーに遺贈する」と明記しておくことが、愛する人を守る唯一の確実な方法です。
行政書士が推奨する
「おふたりさま遺言」の3つのポイント
作成にあたって、以下の実務的なポイントを押さえておきましょう。
「公正証書遺言」を選択する
自筆証書遺言でも有効ですが、兄弟姉妹が納得せず「本人の筆跡ではない」「無理やり書かされた」と争ってくるリスクを最小限にするため、証拠力の高い公正証書遺言を強くお勧めします。
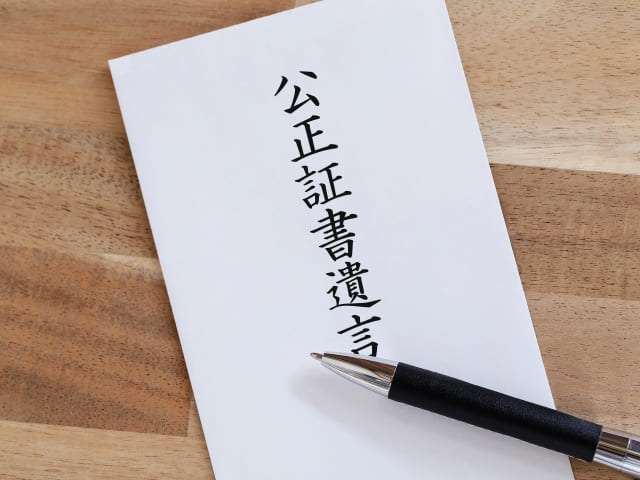
遺言執行者に「配偶者」「専門家」を指名
手続きをスムーズにするため、遺言の内容を実現する責任者である遺言執行者を必ず指定しましょう。
配偶者を指定しておくのが一般的ですが、高齢で手続きが不安な場合は、行政書士を予備の執行者に指定するハイブリッド型がトレンドです。
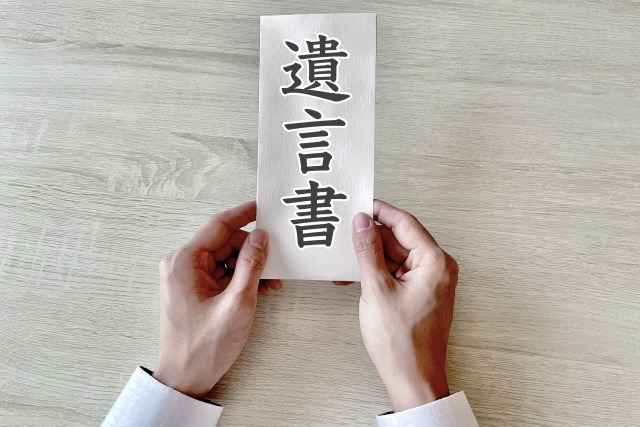
「付言事項」に理由を記す
「兄弟たちへの感謝」と「なぜ配偶者に全財産を遺すのか」という想いを記します。
法的拘束力はありませんが、親族の感情を静め、死後のスムーズな手続きを助ける心理的な防波堤となります。
よくある質問(FAQ)
おふたりさまの遺言は、
配偶者への「最後の護身術」
子供がいない夫婦の相続は、法律が自動的に配偶者を守ってくれるわけではありません。
むしろ、対策をしないと「親族」という名の第三者が介入する仕組みになっています。
- 子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと「配偶者」と「兄弟姉妹(または甥・姪)」が法定相続人になる。
- 兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言書一つで配偶者に全財産を確実に遺すことができる。
- 遺言書がないと、預金解約や不動産の名義変更に義理の兄弟全員の実印が必要になり、生活が凍結されるリスクがある。
- 事実婚やパートナーシップの場合、遺言書がなければパートナーには1円の相続権も、居住権も認められない。
- 2024年の相続登記義務化により、不動産の放置は過料の対象となるため、早急な承継先決定が不可欠。
- 二次相続(配偶者の死後)まで見据えた予備的遺言を添えるのがプロの標準的な設計。
「まだ早い」「うちは大丈夫」という過信が、最愛のパートナーを孤独な法的紛争へと突き落としてしまうかもしれません。
遺言書は、あなたが亡くなった後もあなたの代わりに配偶者を守り続ける、いわば「法的なボディガード」です。
これからの穏やかな夫婦生活を、本当の意味で安心なものにするために。
そして、二人の大切な思い出が詰まった財産を、正しくパートナーに引き継ぐために。今こそ、一通の遺言書を形にしてみませんか。
その決断が、愛する人の未来を100%守り抜く、唯一の確実な手段となります。
どのような家族の形であっても、あなたの深い愛情が法律の壁に阻まれることなく、大切なパートナーへと確実に届くよう、私たちは最新の知見を持って全力でサポートいたします。
