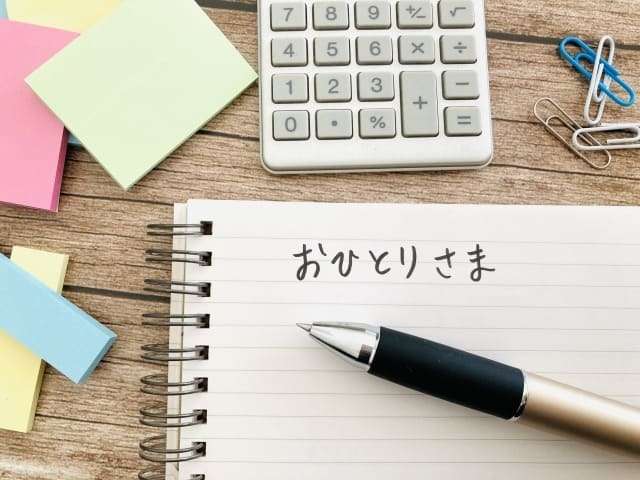※本ページはプロモーションが含まれています。
「自分の後始末」を誰に託しますか?おひとり様が直面する現実
「子供がいないから、自分が死んだら財産は国にいくのかな」
「身寄りがない場合、葬儀や片付けは誰がやってくれるんだろう」
2025年、日本は人口の約3割が65歳以上の高齢者となり、その中でも「おひとり様(単身高齢者)」の割合は過去最高を更新し続けています。
かつては親族が当たり前に行っていた「死後の手続き」ですが、未婚化や核家族化、そして親族関係の希薄化により、「誰にも頼めない」という切実な悩みを抱える方が急増しています。
行政書士の相談現場でよくある誤解が、「遺言書さえ書いておけば、すべて解決する」というものです。
しかし、遺言書はあくまで「財産の分け方」を決める書類。
あなたの死後、病院の精算をし、役所に届け出を出し、部屋を片付け、葬儀を執り行う……
こうした「物理的な作業(事務手続き)」をカバーすることはできません。
今回は、身寄りのない方や親族に負担をかけたくない方が、安心して生き抜くための二段構えの対策「遺言書 × 死後事務委任契約」について解説します。
遺言書だけでは解決できない
「死後の4大ハードル」
おひとり様が亡くなった後、誰かが必ず行わなければならない作業が主に4つあります。
これらは法律上、遺言書の内容には含まれない「事務」の領域です。
医療費・施設費用の精算と退去手続き
入院中や施設入所中に亡くなった場合、未払いの費用が発生します。
また、居室に残された家財道具の処分や清掃、賃貸契約の解約手続きも必要です。
これらは「誰かが動かなければ、いつまでも費用が発生し続ける」性質のものです。
葬儀・埋葬の執行
通夜、告別式、火葬の手配はもちろんのこと、納骨先の管理や永代供養の手続きも含まれます。
特に「特定のお寺に入りたい」「樹木葬がいい」といった希望がある場合、それを実現する「権限」を持つ人を指定しておかなければなりません。
役所への各種届け出と公的年金の停止
死亡届の提出に始まり、健康保険、介護保険の資格喪失、年金の受給停止手続きなど、行政上の手続きは多岐にわたります。
これらは期限が定められており、放置すると不正受給とみなされたり、還付金が受け取れなかったりする不利益が生じます。
デジタル遺品の整理とSNSの閉鎖
スマホの契約解除、サブスクリプションの解約、SNSアカウントの削除など、現代特有の「デジタル後始末」も深刻な問題です。
放置されたアカウントが不正利用されるリスクを避けるためにも、誰かに託す必要があります。
最強の解決策
「死後事務委任契約」とは?
おひとり様の「死後の物理的な不安」を解消するのが、生前に専門家などと結んでおく死後事務委任契約です。
行政書士などが「死後の代理人」になる
この契約は、あなたが元気なうちに、「自分の死後、以下の事務を委任します」と契約を結んでおくものです。
これにより、行政書士などの受任者が、あなたの代わりに正当な権限を持って、銀行口座の解約や葬儀の手配を行うことができるようになります。
契約に含まれる具体的な内容
実務では、以下のような細かな項目まで盛り込むことが一般的です。
- 親族や知人への死亡連絡
- 自宅の片付けと遺品整理、不動産の明渡し
- 飼っているペットの譲渡(新しい飼い主への引き継ぎ)
- デジタル遺産(SNS、クラウドデータ)の消去
- 遺留品の中から形見分けを行う作業
費用はどのように準備するのか?
事務には必ず「実費(葬儀代、片付け代など)」がかかります。
多くの場合、契約時に一定額を預託金(信託口口座などでの管理)として預けるか、遺言書で「事務費用として〇〇万円を執行者に与える」と指定し、死後の財産から支払う仕組みを整えます。

≪遺言編≫
おひとり様の財産はどこへ行く?
事務手続きの不安を解消した次は、いよいよ「財産」の行方を決めます。
相続人がいない場合、財産は「国のもの」
もし遺言書を書かずに亡くなり、法定相続人もいない場合、あなたの財産は最終的に国庫(こっこ)に帰属します。
2024年の相続登記義務化以降、不動産の国庫帰属制度も一部始まりましたが、基本的には「何も残さない」ための手続きは非常に煩雑です。
「お世話になったあの人に」「応援したい団体に」という意志があるなら、必ず遺言書が必要です。
遺贈(いぞう)の活用:感謝を形にする
- 特定遺贈
特定の不動産や預金を、特定の個人や団体に譲る。 - 包括遺贈
財産の全額、あるいは一定割合(例:半分)を譲る。
おひとり様の場合、長年付き合いのあった友人や、従兄弟など、法律上の相続権がない人に財産を渡したいケースが多いです。
これを「遺贈」によって実現します。
遺贈寄付(いぞうきふ)という選択肢
近年、自分の財産をNGOや母校、自治体などに寄付する「遺贈寄付」が非常に注目されています。
2025年現在、多くの団体が専用の相談窓口を設けており、社会に恩返しをしたいという方の想いを支えています。
おひとり様が必ず備えるべき
「3段階の守り」
安心した老後と死後を迎えるためには、以下の3つの契約をセットで検討することが、「終活」のゴールデンルールです。
≪第1段階≫
見守り契約・任意後見契約
「認知症になったとき、誰が自分の生活を支えてくれるか」を備えます。
施設入所の契約や介護サービスの申し込みを、あらかじめ選んだ「任意後見人」に託します。

≪第2段階≫
遺言書(公正証書)
「自分の財産を誰に引き継ぐか」を決めます。
争いを防ぎ、確実に意志を通すためには、公証役場で作る公正証書遺言が必須です。
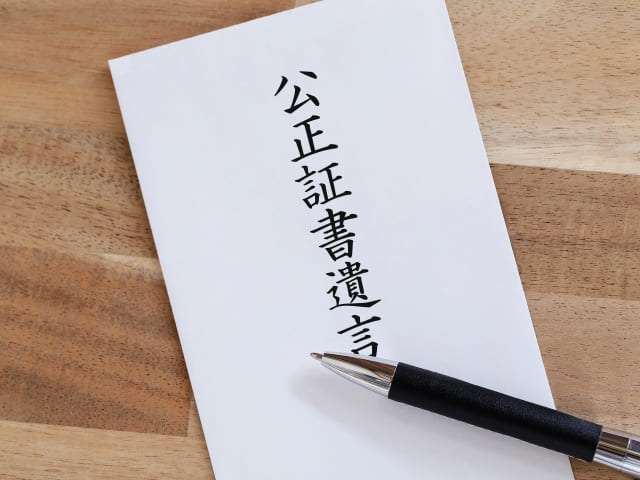
≪第3段階≫
死後事務委任契約
「自分の亡き後、誰が物理的な片付けをしてくれるか」を備えます。
これが欠けると、部屋の片付けが進まず、周囲に多大な迷惑をかけることになります。

≪最新法令≫
相続登記義務化とおひとり様
2024年4月に始まった相続登記の義務化は、おひとり様にも大きな影響を与えています。
空き家問題を自分の死後に作らない
もしあなたが不動産(自宅など)を持っていて、引き継ぎ手を決めていない場合、その家は「所有者不明土地」となってしまうリスクがあります。
遺言書で受取人を指定し、かつ死後事務委任や遺言執行者を定めておくことで、死後速やかに名義変更が行われ、社会問題化している空き家問題の加害者になることを防げます。

遺言執行者の権限強化
最新の法改正により、遺言執行者の権限が明確化されています。
おひとり様の場合、親族の同意を待つ必要がないため、第三者のプロ(行政書士等)を執行者に据えておくことで、非常にスピーディーに不動産の売却や寄付の手続きを進めることが可能です。
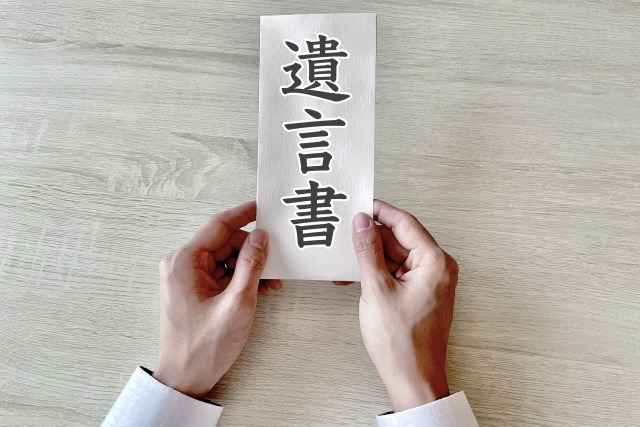
おひとり様が陥りやすい「終活のワナ」
行政書士が現場でよく見る、惜しい失敗事例を紹介します。
「親族に任せれば大丈夫」という思い込み
疎遠な姪や甥にすべてを任せようと考えている方も多いですが、彼らにも自分の生活があります。
死後の手続きは100項目以上に及ぶこともあり、「無償で、かつ多大な時間を使う作業」を親族に押し付けるのは、結果として親族間のトラブルや負担感を生むことになります。
自筆証書遺言の「有効性」の壁
自分で書いた遺言書は、形式不備で無効になるリスクがあります。
特におひとり様の場合、無効になった際の「代わりの解決策(相続人同士の話し合い)」が機能しないため、最初から「鉄壁の公正証書」で作るべきです。
よくある質問(FAQ)
人生の幕引きを
「自分らしく」デザインする
おひとり様の終活は、孤独を恐れるためのものではなく、最後まで自分らしく、誇りを持って生きるための準備です。
- 遺言書は「財産の行き先」を、死後事務委任契約は「物理的な片付け」を担う車の両輪である。
- おひとり様の場合、死後の手続きをプロに託すことで、疎遠な親族への負担をゼロにできる。
- 寄付(遺贈)という選択肢を持つことで、一生をかけて築いた財産を社会に役立てることができる。
- 相続登記の義務化により、不動産を持つおひとり様の「死後放置」は法的なリスクを伴う。
- 見守り・後見・遺言・死後事務の4点セットを整えるのが、2025年の最新かつ最強の防衛策。
- 行政書士は、これらの契約を一本の線で繋ぎ、あなたの人生の「最期の伴走者」として機能する。
「自分の死後のことは分からない」と目を背けるのではなく、すべてに「道筋」をつけておくこと。
それが、残された時間を不安なく、楽しみながら生きるための最大の秘訣です。
私たちが関与させていただいたお客様の中には、死後事務委任と遺言を完成させた瞬間、「憑き物が落ちたように表情が明るくなった」という方がたくさんいらっしゃいます。
人生の最終章を、誰にも迷惑をかけず、感謝と共に締めくくる。そのための準備を、今、一緒に始めましょう。
あなたの「これまで」を尊重し、「これから」を安心で満たすため、私たちは専門知識と真心を込めてサポートし続けます。