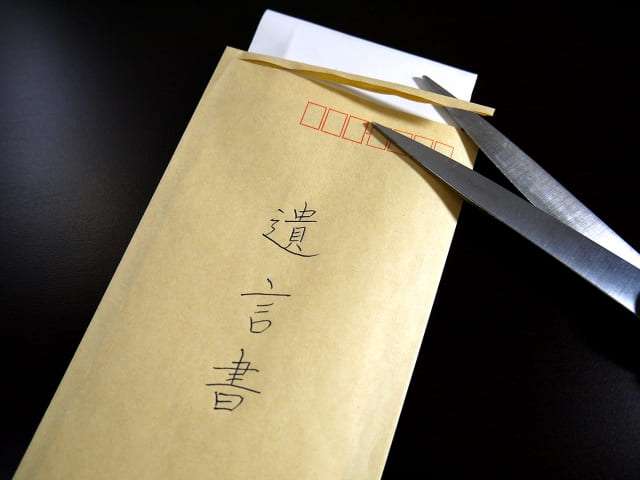※本ページはプロモーションが含まれています。
遺言書発見!その時、あなたが絶対にやってはいけないこと
亡くなった親の整理をしていたら、タンスの奥から「遺言書」と書かれた封筒が出てきた——。
もしあなたがそのような状況に直面したら、まず何をしますか?
「中に何が書いてあるんだろう?」と、その場ですぐに封を開けて中身を確認したくなるのが人情です。
しかし、ちょっと待ってください!
その封筒を勝手に開ける行為は、法律違反になる可能性があります。
最悪の場合、5万円以下の過料を科されたり、他の相続人から「中身を改ざんしたのではないか」と疑われ、相続権を失うトラブル(欠格事由)に発展することさえあります。
自筆の遺言書を発見した場合、最初に行わなければならない法的手続きが「検認(けんにん)」です。
この記事では、行政書士が、検認の目的、具体的な手続きの流れ、2024年の戸籍法改正による書類収集の変化、そして検認を回避する方法までを解説します。
そもそも「検認(けんにん)」とは?
誤解されがちな目的と効果
「検認」という言葉を聞くと、「裁判所が遺言書の内容が正しいと認めてくれる手続き」だと思う方が多いですが、実はそうではありません。
検認の目的は「証拠保全」と「現状確認」
検認とは、家庭裁判所において、相続人全員の立ち会いのもとで遺言書を開封し、その形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認する手続きです。
その目的は、「その時点で遺言書がどのような状態で存在していたか」を記録し、後日の偽造や変造を防止すること(証拠保全)にあります。
検認は「有効・無効」を判断ではない
ここが最大の誤解ポイントです。
検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると「お墨付き」をもらったわけではありません。
たとえ検認済みであっても、認知症で判断能力がない状態で書かれた疑いがある場合などは、別途「遺言無効確認訴訟」で争うことが可能です。
検認はあくまで「外形的な確認」に過ぎないのです。
検認が必要な遺言・不要な遺言
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
特に、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、検認が不要となるため、相続人の負担が大幅に軽減されます。
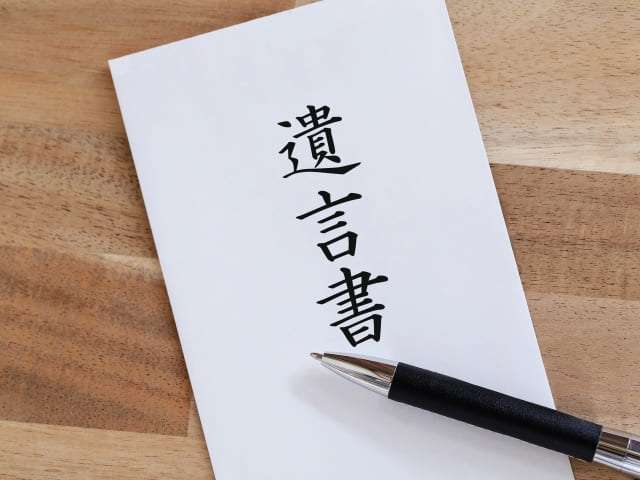
| 遺言の種類 | 保管状況 | 検認の要否 |
| 自筆証書遺言 | 自宅で保管 | 必要 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 法務局で保管(保管制度利用) | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で保管 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 自宅等で保管 | 必要 |
罰則あり!
勝手に開封してしまった場合のリスク
民法1004条・1005条には、遺言書の取り扱いに関する厳格なルールが定められています。
≪リスク1≫
5万円以下の過料(かりょう)
家庭裁判所での検認を経ずに遺言書を開封したり、遺言書を提出しなかったりした場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。これは行政罰の一種です。
「知らなかった」では済まされない場合もあるため、封印のある遺言書は絶対にハサミを入れてはいけません。
≪リスク2≫
相続欠格(そうぞくけっかく)の疑い
より深刻なのがこちらです。
勝手に開封したことで、「自分に有利なように書き換えたのではないか」「都合の悪い部分を破棄したのではないか」と他の相続人から疑われる可能性があります。
もし、「破棄」や「隠匿(隠すこと)」とみなされた場合、民法891条の「相続欠格事由」に該当し、相続権そのものを剥奪されるリスクがあります。
検認手続きの具体的な流れ
(5ステップ)
実際に遺言書が見つかってから、検認を終えて手続きに使えるようになるまでのフローを解説します。
期間は申立てから終了まで1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。
≪ステップ1≫
必要書類の収集(戸籍の壁)
検認を申し立てるには、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
≪2024年3月 戸籍法改正の影響≫
これまでは本籍地の役所ごとに請求する必要がありましたが、広域交付制度の開始により、最寄りの法務局や市区町村役場で「被相続人の出生から死亡までの戸籍」をまとめて請求できるようになりました。
(※ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍や、兄弟姉妹が相続人の場合の兄弟の戸籍などは除外されるケースもあり、注意が必要です)
≪ステップ2≫
家庭裁判所へ「検認の申立て」
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
- 申立人
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人。 - 費用
遺言書1通につき収入印紙800円 + 連絡用の郵便切手代。
≪ステップ3≫
検認期日の通知
裁判所が書類を確認し、問題なければ「検認期日(けんにんきじつ)」(実際に開封する日)が決定され、相続人全員に通知が届きます。
※申立人以外の相続人は、当日に欠席しても手続きは進みます。(不利益にはなりません)
≪ステップ4≫
検認期日当日の立会い・開封
申立人は、遺言書の原本と印鑑を持って家庭裁判所に行きます。
裁判官の前で初めて開封し、内容の確認が行われます。
≪ステップ5≫
「検認済証明書」の申請・受領
検認が終わると、遺言書の原本に「検認済証明書」という表紙のようなものが合綴(がってつ)され、割り印が押されます。
この証明書が付いた遺言書があって初めて、銀行の解約や不動産の名義変更が可能になります。
証明書の発行には別途150円分の収入印紙が必要です。
申立てに必要な書類リストと費用の目安
検認申立ては、書類集めが最大の難関です。
相続関係が複雑(前妻の子がいる、兄弟姉妹が相続人など)な場合は、膨大な量の戸籍が必要になります。
必須書類チェックリスト
- 家事審判申立書(裁判所で入手可能)
- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の住民票の除票(死亡の記載があるもの)
- (遺言書が封印されていない場合)遺言書の写し
ケース別追加書類
- 親や祖父母が相続人の場合
先に死亡している子の出生から死亡までの戸籍など。 - 兄弟姉妹が相続人の場合
両親の出生から死亡までの戸籍など。(親が亡くなっている証明)
費用の目安
- 実費
印紙代800円+切手代(数千円)+戸籍取得費用(数千円〜数万円)。 - 専門家報酬
司法書士や弁護士に申立書作成を依頼する場合、別途数万円〜10万円程度の費用がかかります。
検認が終わった後の手続き(遺言執行)
検認済証明書付きの遺言書が手に入ったら、いよいよ実際の名義変更手続き(遺言執行)がスタートします。
銀行・法務局での手続き解禁
検認済みの遺言書を持参することで、金融機関での預貯金解約・払戻しや、法務局での不動産相続登記(名義変更)が可能になります。
「遺言執行者」が指定されていない場合
遺言書の中で「遺言執行者(手続きを行う代表者)」が指定されていない場合、手続きのたびに相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になるケースがあります。
手続きを円滑に進めるために、家庭裁判所に申し立てて「遺言執行者の選任」を行うことも検討すべきです。
これには行政書士などの専門家が就任することも可能です。
検認を回避するための「生前対策」
ここまで読んで、「検認って面倒くさいな」「残された家族にこんな手間をかけさせたくないな」と思った方も多いでしょう。
検認を回避し、死後すぐに手続きに入れるようにする方法が2つあります。
1. 公正証書遺言を作成する(推奨)
公証人が作成し、公証役場で保管される公正証書遺言は、法律で明確に「検認不要」とされています。
作成に費用はかかりますが、死後の手続きのスピードと確実性は段違いです。
トラブル防止の観点からも最も推奨される方法です。
2. 自筆証書遺言書保管制度を利用する
自分で書いた遺言書を、生前に法務局に預ける制度です。
この制度を利用した場合も、「検認不要」となります。
さらに、法務局で形式不備のチェックを受けられるため、無効リスクも低減できます。手数料も3,900円と安価です。
行政書士に依頼するメリットと役割分担
検認手続きやその後の相続手続きにおいて、行政書士はどのようにサポートできるのでしょうか。
他士業(弁護士・司法書士)との違いも含めて解説します。
面倒な「戸籍収集」の完全代行
検認申立てで最も大変なのが、「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集です。
転籍を繰り返している場合や、兄弟姉妹が相続人の場合、全国各地の役所から何十通もの戸籍を取り寄せる必要があります。
行政書士は、職務権限によりこれらの戸籍収集をすべて代行し、「相続関係説明図」を作成します。
これにより、申立ての準備が劇的にスムーズになります。
検認後の「遺言執行」サポート
検認はあくまで「入口」です。
その後の銀行解約、自動車の名義変更、クレジットカードの解約など、無数にある手続きを「遺言執行者」として、あるいは「遺産整理業務」として代行できるのが行政書士の強みです。
※検認申立書そのものの作成・提出代理は司法書士・弁護士の業務範囲となりますが、行政書士は戸籍収集や遺言執行の面で強力にサポートします。
提携する司法書士と連携し、ワンストップで対応する事務所も多いです。
よくある質問(FAQ)
検認は「ゴール」ではなく「スタート」
遺言書の検認は、故人の想いを実現するための最初の扉を開ける手続きです。
しかし、その扉を開けるには、正しい鍵(手続き)と、慎重な取り扱いが必要です。
- 自筆証書遺言(法務局保管以外)を見つけたら、絶対に開封せず、速やかに家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
- 勝手に開封すると、5万円以下の過料や、最悪の場合は相続権の剥奪(欠格)につながるリスクがあります。
- 検認の目的は証拠保全であり、遺言の有効・無効を判定するものではありません。
- 申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本など、膨大な書類収集が必要となり、準備には専門知識と労力を要します。
- これから遺言を書く方は、残された家族の負担(検認の手間)をなくすために、公正証書遺言か自筆証書遺言書保管制度の利用を強くお勧めします。
遺言書が見つかったけれど、何から手を付ければいいかわからない。
戸籍集めが難しくて進まない。
そんな時は、無理せず行政書士にご相談ください。
複雑な手続きを紐解き、円満な相続の実現をサポートいたします。